1 ~ 1件/全1件
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
ヴェネツィア
15
かつて、'60年代後半から'80年代前半にかけて寺山修司の率いる劇団「天井桟敷」は、世界の演劇界を席巻していた。残念ながら、それをライヴで見ることはできなかったが(もっとも、今も他の劇団による寺山劇の再演はしばしば行われている)、幸いにも彼の残した短歌と俳句は相当な数に上るものがある。短歌は、寺山らしい魔的で情念的な暗さを持つ独特の世界を形成しており、短歌史においても異彩を放っている。「売りにゆく柱時計がふいに鳴る横抱きにして枯野ゆくとき」をはじめ、他では見られない歌がここにはたくさん収録されている。2012/07/31
oz
9
初読。寺山修司(1935-1983)は18歳で中井英夫に見出され、短歌研究誌上に『チェホフ祭』50首を携えて登場。31歳で短歌と袂を分かった。『空には本』は少年の視線から瑞々しく抒情的な歌が多く見られるが、『血と麦』『田園に死す』からは因習と血に呪縛された呪術的な「家」と「母」をめぐる怨嗟と愛憎の歌が展開される。寺山にとっての家とは故郷ひいては国家に連なるコミュニティの最小単位であり、この解体(家出)と固定(愛着)の接続点として「母」があり、「母」は寺山の実際の母を超えたイメージを仮託される存在となった。2016/09/25
宙太郎
2
この本も5月末の青森旅行で訪れた古書店で記念に購入した本。寺山修司氏の死去が1983年5月、この本の初版が同年11月。死去からわずか半年後の出版だ。そのせいか、氏の逝去の衝撃未だ冷めやらずという印象がひしひしと感じられる福島泰樹氏の解説の寺山氏に語りかけるような口調が胸に迫る。早々に作歌から遠ざかってしまった寺山氏だが、そのみずみずしい感性は今もなお色あせない魅力を蔵している。「海を知らぬ少女の前に麦藁帽のわれは両手をひろげていたり」この歌を初めて目にした時の蝉の声まで聞こえそうな感動が忘れられない。2024/06/18
恋々
1
父に借りたもの。 空いた時間に取り出して、どこかのページを開いて、眺めて。それを繰り返すのに適していると思う。暗くて愚かしくて、時々悲しくなる思いが短歌に詰められている。この世界観を色んな人に知ってもらいたいと思いました2012/04/17
hisajun
0
☆☆☆★★(再)2009/05/17


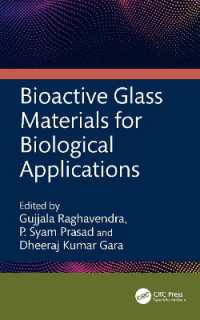

![山本長官機は還らず 連合艦隊司令長官機撃墜作戦 - [空母瑞鶴戦史]ラバウル航空撃滅戦 2 光人社NF文庫 ノンフィクション](../images/goods/ar2/web/imgdata2/47698/4769834020.jpg)



