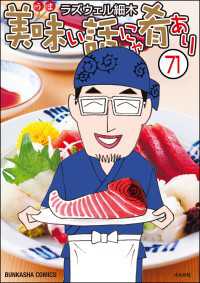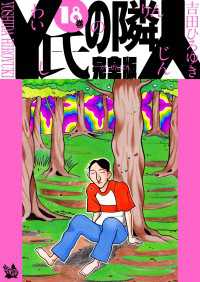目次
第1部 東アジア・西欧と日本(歴史書の歴史(東アジアと日本)
歴史書の歴史(西欧と日本))
第2部 史学概論と歴史理論(史学概論と歴史理論の歴史(1)(1870年~1940年)
史学概論と歴史理論の歴史(2)(1926年~1970年)
史学概論と歴史理論の歴史(3)(1971年~2015年))
著者等紹介
楠家重敏[クスヤシゲトシ]
1952年東京都品川区生まれ。1980年日本大学大学院文学研究科日本史専攻(博士課程後期)修了。現在、杏林大学外国語学部教授、日本大学講師(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
うえ
8
『歴史とは何か』を論じた書物を司馬遷から2015年の保城広至まで広く扱っている。まずガイドブックとして秀逸。著者は明治時代、歴史家と歴史哲学者の噛合わない論争に、歴史家がへそを曲げ歴史哲学を学ばなくなった原因と見、歴史哲学の必要性を説き、広く紹介している。特に日本に2人しかいない歴史理論家、神山四郎と神川正彦を高く評価する。多くの史学者が唯物史観に理論面、道徳面で依拠してきた為ソ連崩壊後、バックボーンをなくし混乱をきたしてきた様子が概観できる。近世という概念を初めて導入した内田銀蔵にも言及している。2017/02/03
さとうしん
2
前半は単なる史学概論のテキストだが、読みどころは1970年代以降の関連書を紹介した第5章。史学史に関するブックガイドとして使うのが正しい読み方かもしれない。現在まで続々と関連書が刊行されているのを見ると、近代以降の日本人にとって「歴史とは何か」というのは永遠のテーマなのかもしれない。2016/04/05
フルボッコス代官
1
史学史本としてはなかなか面白かった。歴史とは何かというテーマはもはや哲学であり、完全解答は不可能であろうとは思うが、歴史が研究されてきた流れをつかむのには史料の紹介も多くてよいと思う。2018/04/24