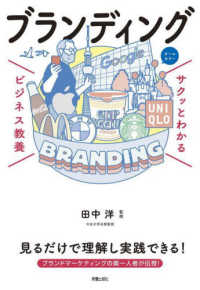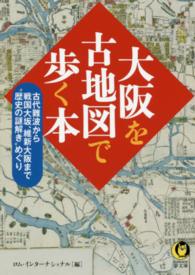内容説明
個々の研究領域を融合し、鮮やかな未来的ビジョンを示すため、今、研究者は何をすべきか?学際複合領域研究の先駆者、慶應義塾大学湘南藤沢キャンパス(SFC)に、そのヒントがある。
目次
1章 コラボレーションから生まれる未来研究(Case No.1「moi」「COLORS」―都市環境におけるメディアデザイン;Case No.2「Airy Notes」―自然環境の視覚化と分析;Case No.3「VNCS」―医療環境を拡張するネットワークシステム形成;Case No.4「IS2」―教育環境を革新する知識の共有と創発)
2章 未来を創る3層研究(「人にやさしい情報環境の構築」次世代インフラ基盤グループ;「基礎技術研究と応用プロトタイプの構築」次世代応用基盤グループ;「ソーシャルソリューションの実験と実践」先端的な基盤実証実験グループ)
3章 コラボレーションの構造(コラボレーションを生み出す基盤と文化;次世代メディア・知的社会基盤におけるコラボの実践;COEを通じて見えてきたコラボレーションモデル)
4章 鼎談 コラボレーションは、次世代の研究スタイルになりうるか―21世紀COEプログラム「次世代メディア・知的社会基盤」の成果をもとに考える
著者等紹介
徳田英幸[トクダヒデユキ]
慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科委員長兼環境情報学部教授。同大学院工学研究科修了。ウォータールー大学Ph.D.。カーネギーメロン大学計算機科学科研究准教授などを経て現職。ユビキタス環境を実現するためのシステム技術、ソフトウェアの研究・開発などに携わる。1952年生まれ
村井純[ムライジュン]
慶應義塾常任理事、慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科委員兼環境情報学部教授
千代倉弘明[チヨクラヒロアキ]
慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科委員兼環境情報学部教授。同大工学部卒業。東京大学博士(工学)。株式会社リコーなどを経て現職。Computer Aided Design、コンピュータグラフィックス、医学におけるCGの応用に関する研究に携わる。ラティス・テクノロジー株式会社取締役会長。1954年生まれ
金子郁容[カネコイクヨウ]
慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科教授兼総合政策学部教授。同大工学部卒業。スタンフォード大学Ph.D.。ウィスコンシン大学計算機学科準教授、一橋大学教授などを経て現職。情報論、ネットワーク論、意思決定論などを通して、ボランタリーな組織原理を探る。1948年生まれ(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
-
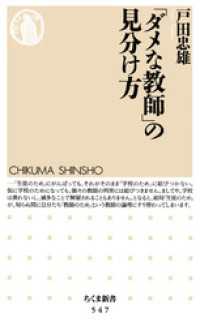
- 電子書籍
- 「ダメな教師」の見分け方 ちくま新書
-

- 電子書籍
- 滝沢の麻雀 勝利への絶対条件