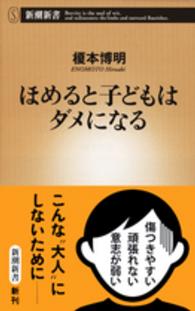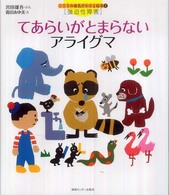内容説明
協同学習の代表的な技法が、実践例で理解できる。技法を使った学級づくりのポイントが分かる。学級の気になる子が授業中に成長する。
目次
1 協同学習で学級をつくる!(協同学習で学級づくりってどういうこと?―今なぜ、協同学習が求められているのか)
2 協同学習を実践してみよう!(みんなで協力する楽しさを味わおう(技法 ダウト)社会
みんなで協力する楽しさを味わおう(技法 ダウト)算数
みんなで団結してみよう(技法 雪だま転がし)国語 ほか)
3 協同学習の技法を使いこなそう!―協同学習の技法活用事典(ダウト;雪だま転がし;お話テープレコーダー ほか)
著者等紹介
石川晋[イシカワシン]
1967年北海道生まれ。北海道上士幌町立上士幌中学校。NPO法人「授業づくりネットワーク」理事
佐内信之[サナイノブユキ]
1970年岡山県生まれ。NPO法人「授業づくりネットワーク」事務局長。元東京都杉並区立方南小学校教諭
阿部隆幸[アベタカユキ]
1965年福島県生まれ。福島県本宮市立糠沢小学校教諭。「東北青年塾」代表。NPO法人「授業づくりネットワーク」理事(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
ぴーたん
1
協同学習の実践例とその解説。紹介されている技法は10あります。先生と生徒の縦の繋がりで学級を作るのではなく、子どもたち同士の繋がりを育てていくことが重要。成り立たせるための条件は4つあり、互恵的な協力関係がある、個人の責任が明確、参加の平等性の確保、活動の同時性が配慮されている。この本に載っている実践はこの条件が揃うように配慮されて構成されているので生徒も安心して取り組むことができるかも。パワーバランスで誰かが押し付けられてやらされたり、模造紙に全員が書けず手持ち無沙汰になったりするしね…。2015/08/01
Ikechan
0
★★★★ 2019/11/18
-
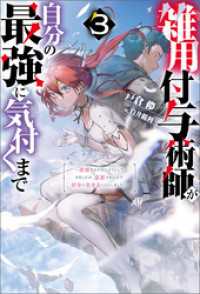
- 電子書籍
- 雑用付与術師が自分の最強に気付くまで~…
-
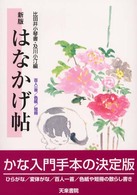
- 和書
- はなかげ帖 (新版)