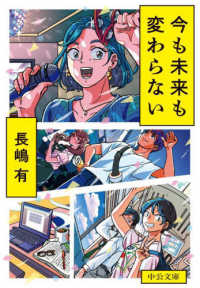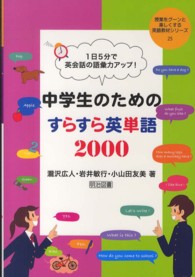出版社内容情報
「ほめても自己肯定感は育たない」「母性の暴走が弊害のもと」……臨床心理学に基づく、日本人必読の書。
頑張れない、傷つきやすい、意志が弱い―― 。生きる力に欠けた若者は、欧米流「ほめて育てる」思想の産物である。その決定的欠陥を臨床心理学データが一刀両断! 教育と人材育成に関わるすべての日本人必読の書。
内容説明
頑張れない、傷つきやすい、意志が弱い。生きる力に欠けた若者たちは、欧米流「ほめて育てる」思想の産物である。一九九〇年代に流入した新しい教育論は、日本社会特有の「甘さ」と結びつき様々な歪みを引き起こした。「ほめても自己肯定感は育たない」「欧米の親は優しい、は大誤解」「母性の暴走が弊害のもと」…臨床心理学データで欧米の真似ごとを一刀両断!教育と人材育成に関わるすべての日本人必読の書。
目次
序章 なぜ「ほめて育てる」が気になるのか
第1章 「注意されることは、攻撃されること」
第2章 欧米の親は優しい、という大誤解
第3章 ほめても自己肯定感は育たない
第4章 日本の親は江戸時代から甘かった
第5章 母性の暴走にブレーキを
著者等紹介
榎本博明[エノモトヒロアキ]
1955(昭和30)年東京都生まれ。心理学博士。東京大学教育心理学科卒業。東芝勤務後、東京都立大学大学院へ。大阪大学大学院助教授等を経てMP人間科学研究所代表。多くの国立・私立大で教えた経験を活かし教育講演を行う(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
1 ~ 1件/全1件
- 評価
購入済の本棚
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
てち
117
私は、塾講師のアルバイトをしている。塾の方針で生徒をたくさん褒めてあげましょうというのがある。しかし、私は褒めることに効果があるのか懐疑的であった。そんな時、本書に出会った。褒めることが悪いのではなく、褒めることしかしないことが悪いのだ。アメとムチみたいに褒めと叱りをうまく使い分けるのが肝要である。2020/06/19
5 よういち
105
褒めて育てることの弊害。◆耳が痛い話しだ。◆欧米は厳しい父性社会、一方、日本は優しく包み込む母性社会。そこを考慮せず、日本的な母子一体感と、ほめて育てるが合体した結果、子どもに以下の弊害が生じた。◆ストレス耐性が低い。自分を振り返らない。頑張ることができない。◆親が先回りして手助けするため、子供は失敗から学ぶことができなくなっている。◆抑圧的な父性に対抗することで心が鍛えられる◆変化の厳しい現在、親も未知である世界を導くことはできない。できるのは、どんな状況でも道を拓けるよう力をつけさせることだけ。2019/12/16
マエダ
83
基本はこの本に賛成である。2016/10/24
パフちゃん@かのん変更
74
今はどうだか分からないが少し前までは「ほめて育てよう」が主流で、通知簿でもマイナスの表現が禁止されるようになった。だが、ほめられて育った子はほめられないと意欲をなくす。失敗を恐れる。注意されると反発し、反省しない。挫折に弱く、逆境を乗り越えられない。などの弊害が表れてきた。自己肯定感の土台になるのは親子の間の心の絆である。日本文化に基づく婉曲的なしつけ「そんなことをしたら笑われるよ」「お巡りさんに叱られるよ」「いい子だからやめようね」というしつけ方も効果があった。2016/05/14
terve
43
最近、子どもの機嫌を取る親が多いですね。実際、我が子を注意できない親もよく見かけます。教師が叱れないことから考えると教育現場でも同じでしょうね。とはいえ、日本と海外では文化の基底が違います。安易に是非を言うべきではありませんよね。それなのに、教育制度に関してはなぜか検討もせず安易に判断を下す(センター試験に変わる記述式なんかその最たる例ですよね。延期になりましたが・・・)ことが多いような・・・。結局お上が頭でっかちなんでしょう。いずれにせよ、子どもと向き合える大人が少なくなってきたといえそうです。2020/01/07