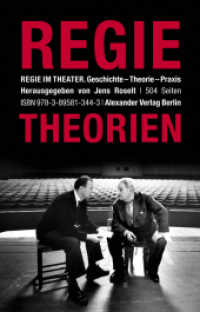出版社内容情報
《内容》 現在,「栄養士法の一部を改正する法律」の施行に伴い,改訂された管理栄養士の養成カリキュラムが行われており,本書はこのような状況に対応すべく企画された『基礎栄養学』である.
本書の内容は,管理栄養士の養成カリキュラムを履修していく過程の,おそらく早い段階で学ぶものであろう.したがって,科学的な視点を基に,栄養学の基本から全体を体系的に学習できることを目的とし,編集にあたっては,管理栄養士国家試験出題基準(ガイドライン)に従った.まず,栄養の定義と栄養学の歴史について理解を深め,栄養素の吸収・代謝の機構と生理的役割がスムーズに理解できるよう配置している.また,栄養状態の判定方法,エネルギー代謝,栄養素の分子生物学的役割などを学習することにより,栄養素が生体で利用される過程を理解し,栄養と健康とのかかわりについての理解力が自然に養われるよう構成した.
とくに「8章 エネルギー代謝」では,食物から得られるエネルギーの生体内での利用とエネルギー所要量の概念を容易に理解できるよう,エネルギー量の算出の具体例を用いて解説した.また,生活習慣病などの予防を個人の遺伝的体質に基づいて行うテーラーメイド予防への期待が高まっているなか,新しい分野である分子栄養学の基本的知識が得られる「9章 遺伝子発現と栄養」を加えている.
執筆は基礎栄養学の分野で教育と研究に携わっている専門の方々にお願いし,内容が的確に理解できるように図表を多く取り入れていただいた.重要な用語は太字で示し,各章末には新しい国家試験の予想問題を付している.国家試験を受験する際にも,むだなく準備ができるよう配慮した.
《目次》
基礎栄養学・目次
1章 栄養
1.1 栄養,栄養素,食品
1.2 生体成分としての栄養素
1.3 食品成分としての栄養素
1.4 栄養学史
1.4.1 呼吸とエネルギー代謝
1.4.2 三大栄養素の消化と利用
1.4.3 出納実験およびタンパク質の栄養価
1.4.4 ビタミンの発見
1.4.5 無機質の栄養
予想問題
2章 栄養と食生活
2.1 健康と食生活
2.2 ライフステージと食生活
2.3 食物摂取の体内調節
2.4 生体リズムと食生活
予想問題
3章 栄養と疾病
3.1 疾病と食生活
3.1.1 欠乏症
3.1.2 過剰症
3.1.3 現在は欠乏症も過剰症もある
3.1.4 生活習慣病の概念
3.1.5 疾病の推移,予防,治療と食生活
3.2 疾患と栄養管理
3.2.1 治療食
3.2.2 摂食・消化吸収能と栄養補給
3.2.3 疾病管理
3.3 生体防御と栄養
3.3.1 生体防御の最初の段階,皮膚
3.4 栄養状態の評価
3.4.1 栄養状態と身体状態
3.4.2 身体計測と身体機能による評価
3.4.3 臨床医学的検査および生化学的検査による評価
3.4.4 臨床検査と栄養
3.4.5 食事(栄養)調査の方法と栄養摂取状況の評価
3.4.6 個人または集団への栄養介入のデザイン,評価,フィードバック
予想問題
4章 栄養素の構造と機能
4.1 糖質の栄養
4.1.1構造
4.1.2血糖とその調節
4.1.3エネルギー源としての作用
4.1.4他の栄養素との関係
4.2 脂質の栄養
4.2.1構造
4.2.2脂質の臓器間輸送
4.2.3貯蔵エネルギーとしての作用
4.2.4コレステロールの体内バランス
4.2.5他の栄養素との関係
4.3 タンパク質の栄養
4.3.1アミノ酸
4.3.2ペプチド
4.3.3タンパク質
4.3.4タンパク質の機能
4.3.5アミノ酸の臓器間輸送
4.3.6タンパク質の栄養価
4.3.7他の栄養素との関係
4.4 ビタミンの栄養
4.4.1構造
4.4.2ビタミンの栄養学的機能
4.4.3ビタミンの生物学的利用度
4.4.4他の栄養素との関係
4.5 無機質の栄養
4.5.1無機質の分類と栄養学的機能
4.5.2硬組織と無機質
4.5.3生体機能の調節作用
4.5.4酵素反応の賦活作用
4.5.5他の栄養素との関係
4.6 機能性非栄養成分
4.6.1 食物繊維,難消化性オリゴ糖,香辛料等
予想問題
5章 栄養素の消化と吸収
5.1 消化・吸収の基本概念
5.2 消化器と消化管
5.3 消化の仕組み
5.4 消化管での消化・消化過程
5.5 吸収のしくみ
5.6 栄養素の吸収経路
5.7 糞便の形成
5.8 消化・吸収の調節
5.9 生物学的利用度
5.10 腸内細菌叢とその役割
予想問題
6章 栄養素の代謝
6.1 糖質の代謝
6.1.1 代謝経路
6.1.2 解糖
6.1.3 クエン酸回路
6.1.4 糖新生と糖質合成
6.1.5 食後,食間期の糖質代謝,糖質代謝の臓器差
6.2 脂質の代謝
6.2.1 代謝経路
6.2.2 脂肪酸の生合成
6.2.3 脂肪酸の酸化
6.2.4 不飽和脂肪酸の代謝
6.2.5 アシルグリセロール・リン脂質・糖脂質の代謝
6.2.6 コレステロールの合成・輸送・蓄積
6.2.7 食後,食間期の脂質代謝,脂質代謝の臓器差
6.3 タンパク質・アミノ酸の代謝
6.3.1 アルブミン
6.3.2 急速代謝回転タンパク質(RTP)
6.3.3 アミノ基転移反応
6.3.4 非必須アミノ酸の生合成
6.3.5 タンパク質,アミノ酸の異化(脱アミノ基反応と尿素の生成を含む)
6.3.6 アミノ酸の特殊生成物への変換(ポルフィリン,胆汁色素,クレアチニン等)
6.3.7 食後,食間期のタンパク質代謝,タンパク質代謝の臓器差
6.4 ビタミンの代謝
6.5 無機質の代謝
6.6 代謝経路の調節
予想問題
7章 水・電解質の代謝
7.1 水の出納
7.1.1 代謝水
7.1.2 不感蒸泄
7.1.3 不可避水分摂取量
7.1.4 不可避尿量等)
7.2 電解質の代謝
7.2.1 水・電解質・酸塩基平衡の調節
7.2.2 高血圧とナトリウム・カリウムなど
予想問題
8章 エネルギー代謝
8.1 エネルギーとその単位
8.2 食品のエネルギー量
8.3 栄養素の体内での生理的エネルギー量
8.3.1 栄養素の物理的燃焼値と生理的燃焼値
8.4 細胞レベルでのエネルギーの利用状態
8.4.1 ATPの役割
8.4.2 生体酸化
8.4.3 呼吸鎖と酸化的リン酸化
8.5 エネルギー消費量
8.6 エネルギー代謝の測定法
8.7 エネルギー所要量の算定と生活活動強度
予想問題
第九章 遺伝子発現と栄養
9.1 情報高分子の構造と機能
9.1.1 ヌクレオチド
9.1.2 プリン・ピリミジンヌクレオチドの代謝
9.1.3 遺伝子,核酸
9.1.4 タンパク質生合成
9.1.5 遺伝子発現の調節
9.1.6 遺伝子操作
9.2 遺伝形質と栄養の相互作用
9.2.1 生活習慣病と遺伝子多型
9.2.2 倹約(節約)遺伝子仮説
9.2.3 栄養指標としての遺伝子型
9.3 後天的遺伝子変異と栄養素・非栄養素成分
9.3.1 がんのプロモーション,イニシエーションの抑制
9.3.2 植物性抗酸化物質の作用
予想問題
内容説明
本書の内容は、管理栄養士の養成カリキュラムを履修していく過程の、おそらく早い段階で学ぶものであろう。したがって、科学的な視点をもとに、栄養学の基本から全体を体系的に学習できることを目的とし、編集にあたっては、管理栄養士国家試験出題基準(ガイドライン)に従った。まず、栄養の定義と栄養学の歴史について理解を深め、栄養素の吸収・代謝の機構と生理的役割がスムーズに理解できるよう配置している。また、栄養状態の判定方法、エネルギー代謝、栄養素の分子生物学的役割などを学習することにより、栄養素が生体で利用される過程を理解し、栄養と健康とのかかわりについての理解力が自然に養われるよう構成した。
目次
1章 栄養
2章 栄養と食生活
3章 栄養と疾病
4章 栄養素の構造と機能
5章 栄養素の消化と吸収
6章 栄養素の代謝
7章 水・電解質の代謝
8章 エネルギーの代謝
9章 遺伝子発現と栄養
著者等紹介
坂井堅太郎[サカイケンタロウ]
1958年福岡県生まれ。1985年長崎大学大学院水産学研究科修了。現在、広島女学院大学生活科学部助教授。博士(栄養学)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。