出版社内容情報
中世におけるさまざまな表現の営為とそれを支える言語(言語資料)・言語意識を考察した、最新の研究成果を集成。龍谷大学仏教文化研究所の研究プロジェクトを契機として展開された最新の研究の成果を集成し、中世におけるさまざまな表現の営為とそれを支える言語(言語資料)・言語意識を考察する論文とともに、中世文学についての後代の言説を論じた論文をも加えた論文集である。
まえがき
第一章 中世の資料と言語
『職原抄』訓点本の資料性について―龍谷大学本を手懸かりとして― 宇都宮啓吾
龍谷大学図書館蔵『異名盡?名字盡』の語彙について 三宅えり
親鸞自筆『教行信証』に付された角点の基礎的研究 能美潤史
龍谷大学図書館写字台文庫蔵『舟水和謌集』について 檜垣 駿
鎌倉時代の言語規範に関する一考察―「古」なるものへの意識をめぐる― 山本真吾
第二章 中世の表現
建久六年民部卿経房家歌合の俊成歌について 安井重雄
定家の歌語意識と改作―「閨の月影」の歌をめぐって― 溝端悠朗
官職名を詠む和歌 佐藤明浩
『源平盛衰記』烏帽子折物語の成立過程 浜畑圭吾
天草版『平家物語』の感嘆符―付加の規則と物語解釈― 中本 茜
『エソポのハブラス』本文考―「狐と野牛の事」のyuguetano vchiniをめぐって― 水谷俊信
中世王朝物語における音楽―改作本『夜寝覚物語』における箏の琴と琵琶をめぐって― 藤井華子
中世人の「夢の浮橋」―『山路の露』と紫式部堕地獄説話― 亀井久美子
第三章 中世へのまなざし
カール・フローレンツ『日本文学史』の「中世」理解 藤田保幸
第二次大戦下の小林秀雄と〈中世〉―同時代言説を視座として― 田中裕也
藤田保幸[フジタヤスユキ]
編集
内容説明
龍谷大学仏教文化研究所の研究プロジェクト「龍谷大学図書館蔵中世国語資料の研究」を契機として展開された最新の研究の成果を集成した論文集であり、「言語文化」を表現の文化ととらえ、中世におけるさまざまな表現の営為とそれを支える言語(言語資料)・言語意識を考察する論文を収めるとともに、中世文学についての後代の言説を論じた論文も加えた研究書である。
目次
第1章 中世の資料と言語(『職原抄』訓点本の資料性について―龍谷大学本を手懸かりとして;龍谷大学図書館蔵『異名盡并名字盡』の語彙について;親鸞自筆『教行信証』に付された角点の基礎的研究;龍心大学図書館写字台文庫蔵『舟水和謌集』について ほか)
第2章 中世の表現(建久六年民部卿経房家歌合の俊成歌について;定家の歌語意識と改作―「閨の月影」の歌をめぐって;官職名を詠む和歌;『源平盛衰記』烏帽子折物語の成立過程 ほか)
第3章 中世へのまなざし(カール・フローレンツ『日本文学史』の「中世」理解;第二次大戦下の小林秀雄と“中世”―同時代言説を視座として)
著者等紹介
藤田保幸[フジタヤスユキ]
龍谷大学文学部教授。博士(文学)(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
-
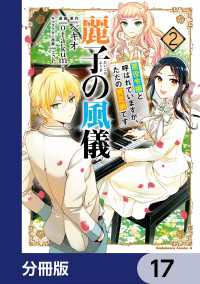
- 電子書籍
- 麗子の風儀 悪役令嬢と呼ばれていますが…







