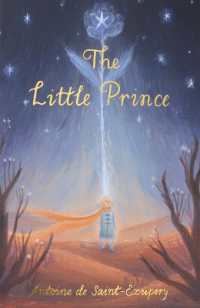- ホーム
- > 和書
- > 教養
- > ライトエッセイ
- > ライトエッセイその他
内容説明
くいしん坊コミュニティデザイナー山崎亮が、日本各地から世界まで、地元の特産や地域密着グルメをいただきながら考えた、まちのこと、ごはんのこと。
目次
二〇一二年(黄楊の餃子;亀乃のハンバーグカレー ほか)
二〇一三年(ヨッサンラーメンの鍋;回転大漁寿司の地魚寿司 ほか)
二〇一四年(宝雲亭のスープ餃子;ひらのやのえびおろし蕎麦 ほか)
二〇一五年(ALEのシカゴスタイルピザ;佐木島のいしじみかん ほか)
二〇一六年(永華麺家のエビワンタン麺;番所亭のすば ほか
著者等紹介
山崎亮[ヤマザキリョウ]
studio‐L代表。東北芸術工科大学教授(コミュニティデザイン学科学科長)。慶応義塾大学特別招聘教授。1973年愛知県生まれ。大阪府立大学大学院および東京大学大学院修了。博士(工学)。建築・ランドスケープ設計事務所を経て、2005年にstudio‐Lを設立。地域の課題を地域に住む人たちが解決するためのコミュニティデザインに携わる。まちづくりのワークショップ、住民参加型の総合計画づくり、市民参加形のパークマネジメントなどに関するプロジェクトが多い(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
1 ~ 1件/全1件
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
けんとまん1007
52
人が住むところには、コミュニティがあり、ごはんがある。コミュニティもどう考えるかで、捉え方が広がる。コミュニティをどう維持するのか、作るのか・・は、今の自分のテーマの一つ。山崎さんとはレベルが違い過ぎるが、自分自身が暮らす地域のことには、眼が向くし、思いもある。そこでの素材の一つが食べることとも思う。美味しいと思える御飯があり、それを作るいhとがいる。一つの家庭の中でも言えることだとも思う。2025/05/15
tetsubun1000mg
19
2017年の再読本だったが、鹿児島のマルヤガーデンの肉屋さんのエピソードで気がついたのだが1/3も読んでから。 時間が掛かるようになってきたなあ。 気がつくだけましか。 でも読んでいくと止めらなくなってきて最後まで読んでしまった。 2ページ半ぐらいでちょうど読みやすいんだよね。 昨年9月に「地域ごはん日記おかわり」が出ているようなので読んでみよう。 山崎氏が訪問、講演した現地の方と地方のおいしいものにトライして喜んでいる様子が微笑ましい。2023/02/23
きゅー
10
著者は地域の課題を地域に住む人たちが解決するためのコミュニティデザインに携わっているという。彼は様々な場所で講演し、ワークショップを開催している。そして、その土地で出会った食べものについての紹介記事を纏めたものが本書だ。そのため、食レポ的に“どのように美味しい”という観点ではなく、その食べもの(料理、作り手)がどのような経緯で生まれ、根付いたかを観察しているのが新鮮で、この本を特別なものとしている。山崎氏も「まちの味を通して感じた地域の特徴を紹介していきたい」と書いているが、その企図は十分に伝わった。2018/04/09
yyrn
7
全国各地(ときどき海外)から呼ばれて町づくりや地域の活性化策を地元の人たちと考えカタチにする仕事をしているコミュニティデザイナーの作者が、訪れた先で食した気取らない料理の数々を仕事で出会った人たちとの交流を絡めてさらりと紹介している本。2012年から16年までの5年間で紹介するのは北海道5、東北8、関東3、中部12、近畿4、中国7、四国6、九州9の29都道県54市町+海外6か国なのだから驚く。単なる講演会もあるようだが、でもそんなに首を突っ込んでイイ仕事ってできるの?そっちの方が料理よりも気になった(笑)2017/03/02
MatsuNoHon
4
山崎さんが地域を訪れた時に聞くのが「普段いく中で一番美味しい店ってどこか」。 地域に根ざした美味しいものには、地域の特徴、力が現れている。 山崎さんの料理の絵も親しみやすく美味しそう。 地域のコミュニティに認知されているものを見つけて来れるのは、山崎さんの飛び込む力によるところが大きいなーと思った。 うらやましいなー(笑)2018/09/15
-

- 電子書籍
- 経験値貯蓄でのんびり傷心旅行【分冊版】…