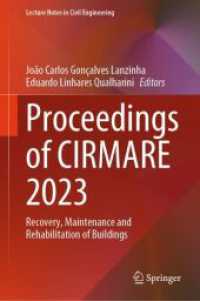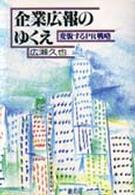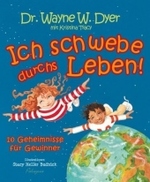目次
移行対象と移行現象
夢を見ること、空想すること、生きること―一次的解離を記述するケース・ヒストリー
遊ぶこと―理論的記述
遊ぶこと―創造的活動と自己の探求
創造性とその諸起源
対象の使用と同一化を通して関係すること
文化的体験の位置づけ
私たちの生きている場所
子どもの発達における母親と家族の鏡‐役割
本能欲動とは別に交叉同一化において相互に関係すること
青年期発達の現代的概念とその高等教育への示唆
著者等紹介
橋本雅雄[ハシモトマサオ]
1942年栃木県に生まれる。1968年慶応義塾大学医学部卒業、医学博士。現職、医療法人社団こころの会田町クリニック院長
大矢泰士[オオヤヤスシ]
1963年生まれ。東京大学文学部、教育学部教育心理学科卒業。東京都立大学大学院人文科学研究科心理学専攻博士課程単位取得。専攻、臨床心理学、精神分析学。現職、東京国際大学大学院臨床心理学研究科准教授。青山心理臨床教育センター臨床心理士(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
またの名
9
「その後続けてこの患者は、ラカンの論文を知っているので、鏡像段階について語った」みたいな治療場面を発生させる患者の知識水準がヤバい。ラカンを参照した部分とラカン本人が後に参照する部分を多く含み何派の理論だか混乱してくる特異な本書は、個人の内面とも外部世界ともすっきり区別できない中間領域の遊びに、精神分析や社会生活ひいては文明の基礎を見る。指しゃぶりから毛布の端やテディベアなど様々な形をとる自分自身ではない所有物として遊ばれる、移行対象。患者と治療者の二つの遊び領域を重ねて創造的に遊べることの必要性を説く。2024/11/20
PukaPuka
2
明らかに旧訳より読みやすい。臨床観察に基づく解釈。 2017/10/30
なっしー
1
原著と併せて読んできた本。原著を読んでいると、ところどころ訳がおかしな点があったり、読みづらかったりするところがあった。やはり原著にあたることの大切さを実感した。内容は、さっぱりわからない。例えば、p15の「私が中間領域と呼んでいるのは、一次的創造性と、現実検討にもとづく客観的知覚とのあいだで、乳児に許されている領域である」とかp36の強固に組織化された解離とは何なのか。中間領域、可能性空間、文化的体験、創造性、このあたり、まだまだ咀嚼できていない。2022/07/18
いとう・しんご
1
自我の確立はフロイト的な性的衝動の挫折により起こるのではない、「赤ちゃんと母親といういまや互いに分離した存在の、 分離状態の始まり」p133にあった愛情と安心に満ちた「可能性空間」における「遊び」をとおして獲得されるのだ、という主張で、とても感動的だし、説得力がある。小児科医としての長年の臨床経験に基づいた本でもあり、赤ちゃんの誕生を待つカップルにお奨めです。2021/03/21
しょうゆ
1
ウィニコットの著作を初めてしっかり読んだ。詩的な表現、難解と呼ばれるのもうなづける。しかし、有名な名言が出てくるところは、「おお」と唸ってしまった。そして、ありていな言い方だが、深みが尋常ではない。このレベルの創作物の後に、軽めの専門書を読むと、ものすごく薄っぺらく感じる。偉大。2020/05/13