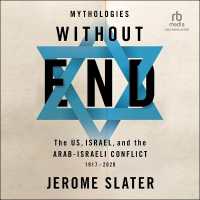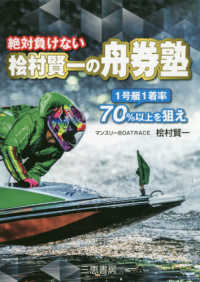目次
第1章 価値を語る三つの方法
第2章 交換理論の現在の潮流
第3章 行為の重要性としての価値
第4章 行為と反影、あるいは富と力の理論へむけての覚書
第5章 ワンパムとイロコイの社会的創造力
第6章 マルセル・モース再訪
第7章 私たちの夢の偽硬貨、またはフェティッシュの問題3b
著者等紹介
グレーバー,デヴィッド[グレーバー,デヴィッド] [Graeber,David]
1961年ニューヨーク生まれ。ニューヨーク州立大学パーチェス校卒業。シカゴ大学大学院人類学研究科博士課程(1984‐1996)修了、PhD。イェール大学助教授、ロンドン大学ゴールドスミス校講師を経て、2013年からロンドン・スクール・オブ・エコノミクス教授。2020年死去
藤倉達郎[フジクラタツロウ]
1966年京都生まれ。アーモスト大学卒業。イェール・ロー・スクール修士課程修了、LL.M.。シカゴ大学大学院人類学研究科博士課程(1992‐2004)修了、PhD.。現在、京都大学大学院アジア・アフリカ地域研究研究科教授。専門は人類学と南アジア地域研究。特にネパール・ヒマーラヤ地域における社会運動や開発現象などについて調査を行なっている(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
月をみるもの
18
経済人=ホモ・エコノミクスが求める「利益」は、究極的かつプライスレスな個人的・社会的価値と、どう一致しどう異なるのか? 「意味」=言語体系の中での差異だとするならば、「意味のない価値」「価値のない意味」は存在するのか? 交換されるふたつのものが同じ「価値」をもつのなら、なぜわざわざそれらを交換するのか? グレーバーの思想の原点がここにある。2023/02/23
roughfractus02
9
著者はアダム・スミスに始まる富のイメージを「夢の偽通貨」と呼ぶ。このイメージはマルクスの余剰価値という負の側とジヴォンズの普遍的希少価値という正の側に分かれ、東西冷戦以後は後者が市場原理主義によって隆盛を誇ってきた。人類学者の著者はこの分岐点に立ち戻って人類学的な贈与経済を重ね、これら「偽通貨」が個人を単位とした所有と消費の流れしか生まないキリスト教的・ヨーロッパ中心的な「夢」と見なす。ここから本書は、マルクスの剰余価値を転倒し、余剰となった富を共同で贈与する経済をベースに、現代の「偽通貨」を鋳造し直す。2025/01/23
翔
9
5度目の読了。読めば読むほどわからんくなってきているような、でも大筋の論述の流れはわかっているような。部族の話あたりから少し蛇足のような気もしてくるけど、何回も読んでるからなんだろうなと思う。その部分に至るまでに書かれている主張に対する裏付けの意味合いが強いように思う。2023/04/30
翔
9
4度目の読了。さすがに話の流れは掴めてきた。気がする。あとは考え方をトレースして視座が同じようなところ、せめて近いところまで届くとグレーバーに見えていた景色が見えてくるような気がする。2023/04/17
翔
9
グレーバー氏のデビュー作。それゆえにテーマの幅が広く、そう簡単に理解できるものではない(その証拠に翻訳版が10年以上経ってから日本で出版されている)。原著から考えると本書から派生してその後の書籍が出ているとも言えるので、順番としては本書を読んでから負債論などを読むと過程が理解しやすいこともあるのかもしれない。本書の後半に訳者の解説が書かれているのでそちらを読んでから本文を読むことで多少なりとも理解しやすくなるかもしれない。2023/03/11