- ホーム
- > 和書
- > 人文
- > 文化・民俗
- > 文化・民俗事情(日本)
内容説明
クース(古酒)の島を守り育てる。県民の4人に1人が犠牲になった壮絶な沖縄戦。すべてが灰燼に帰し歴史的な遺産である古酒も失った廃墟から琉球泡盛はどうよみがえったか。旨い酒を育てるため、二度と戦争のない平和な時代を築くことを決意し、行動した人びと。琉球文化と泡盛600年の歴史とドラマをふりかえる。
目次
序章 歴史的瞬間に立ち会う
第1章 壮絶な地上戦を生きのびて
第2章 首里人の誇り
第3章 クースの番人
第4章 竜宮通りの赤提灯
第5章 県民斯く戦えり
第6章 平和を守る闘い
著者等紹介
上野敏彦[ウエノトシヒコ]
記録作家、コラムニスト、文芸誌「新・新思潮」同人。1955年神奈川県生まれ。横浜国立大学経済学部を卒業し、79年より共同通信記者。社会部次長、編集委員兼論説委員、宮崎支局長などを務める。民俗学者・宮本常一の影響を受けて北方領土から与那国島までの日本列島各地を取材で歩く。酒や食、漁業、朝鮮、沖縄、近現代史をテーマに執筆。共同通信では戦後70年企画『ゼロからの希望』『追想メモリアル』などを担当。宮崎日日新聞にコラム『田の神通信』『新日向風土記』を、高知新聞に大型連載『黒潮還流』をそれぞれ執筆した(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
kawa
34
沖縄戦で100年を超える古酒がすべては灰燼に帰したという。泡盛の戦後の歴史は、ガレキのなかから製造に必要な黒麹菌を見つけ出した咲本酒造・佐久本正良氏から始まる。その後の経緯をクース(古酒)の番人と呼ばれる「居酒屋うりずん」の店主・土屋實幸と、泡盛の御意見番「醸界飲料新聞」主宰の仲村征幸両氏の活動を中心にドキュメント。戦いと泡盛、なかなか繋がりにくいテーマに挑んだ著者にまずは拍手。戦いの経緯をある程度掴んでいる読み手として興味深く読了。海洋博で供され幻の銘酒の作り手とされる宮里酒造所の話題も触れられ初知り。2024/03/10
二人娘の父
8
神亀(日本酒)を主題にした「闘う日本酒」や、震災から復興し蔵を存続させた磐城寿(日本酒)を主題にした「福島で酒をつくりたい」の著者であることを読後に確認し、納得。お酒への愛情は言うまでもなく、そこにジャーナリストらしく、沖縄戦と蔵人たちとの歴史が地続きになっていることが明らかにされる。当然だが、沖縄戦抜きに、現在の沖縄の食や酒、文化などあらゆることは語れない。その視点と丁寧な取材姿勢にあらためて敬意を感じさせられた著作だ。読後、とにかく「カリー春雨」が飲みたくなります。2023/08/24
林克也
3
あの戦争がなかったら、私のような、沖縄・琉球に縁もゆかりも無い本土の人間は、今のように泡盛を楽しむことができなかったのかもしれないと思うと、何とも複雑な気持ちになる。 残りの人生で、47蔵すべての泡盛を飲むことは、できないだろうが、できるだけ多くの銘柄の泡盛を飲んでみたいと思う。 ところで、「新聞が軍部に屈服して、事実を事実として報道できなくなった時代の紙面である」という一文があったが、まさに今、2023年2月も同じである。今は、ここでいう軍部は、統一教会またはアメリカ軍事産業か、という違いはあるが。 2023/02/01
よっちゃん
3
泡盛について良く調査まとめた本。泡盛の奥深さや、戦争で破壊し尽くされた中から関係者の努力で復活させることが出来、味わうことが出来る様になって来た感謝の思いが湧き出て来た。子孫に向けて、古酒を仕込み繫いで行きたいと思う。2022/11/18
-

- 洋書電子書籍
- オックスフォード版 討議民主主義ハンド…
-
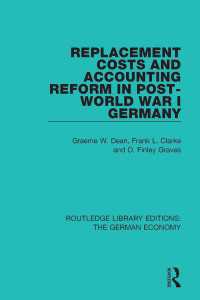
- 洋書電子書籍
- Replacement Costs a…





