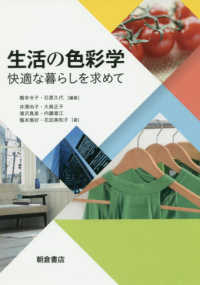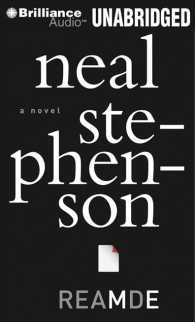目次
第1部 子どもの貧困問題と法制度・学校の体制(社会・地域を変える生活困窮者自立支援法と子どもの貧困対策法を目指して;「チーム学校」は子どもの困難に向き合う学校をつくれるのか―子どもの権利条約の視点から考える;就学援助制度の活用に向けて―お金の心配なく学校生活を送ってもらうために)
第2部 調査研究(調査から見る子どもの貧困と学校の関係;生活困窮世帯の子どもに見られる社会関係と心理面の特徴;学校教員から子どもの貧困はどう見えているのか(その1)―教員の貧困問題の認識、支援経験、法制度の理解度
学校教員から子どもの貧困はどう見えているのか(その2)―教員が感じている貧困の現状と支援の課題
学習支援と新自由主義教育政策)
第3部 現場からの実践報告(スクールソーシャルワーカーは子どもの貧困対策の切り札になるか?―活動実態と職務内容の検討を中心に;「子どもの貧困」と心理支援―学校現場から;なごや子ども応援委員会の活動から見るチーム学校;生活困窮者自立支援制度における現場での支援;生活困窮者支援としての学習支援とは;民間のフリースクール・通信制高校に期待される役割;生きづらさを抱える生徒に寄り添う校内居場所カフェ;子どものくらしに対する教師の感度)
第4部 学校とつながるために(学校とつながるために―子どもと学校を中心にした地域づくり)
著者等紹介
吉住隆弘[ヨシズミタカヒロ]
中部大学人文学部・准教授。臨床心理士、公認心理師、NPO法人ささしまサポートセンター理事。2008年よりホームレス等、生活困窮者支援に携わり、現在は名古屋市と春日井市の生活困窮世帯の子どもの学習支援事業に従事
川口洋誉[カワグチヒロタカ]
愛知工業大学基礎教育センター・准教授。愛知県瀬戸市において学習支援事業「学習教室ピース」を主宰
鈴木晶子[スズキアキコ]
特定非営利活動法人パノラマ・理事。臨床心理士。大学院在学中よりひきこもり支援に関わり、若年無業者支援、生活困窮者支援等の現場を経験。生活に困難を抱える女性、若者、子どもの支援を中心に活動している。インクルージョンネットかながわ代表理事などを歴任(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
ゆう。
Akihiro Nishio
-
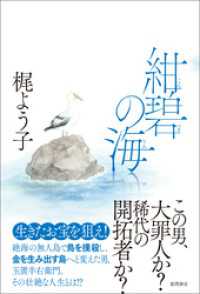
- 電子書籍
- 紺碧の海