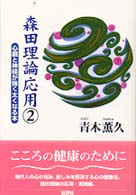内容説明
地球上の7人に1人、10億の民がスラムの住人。都市は貧困で爆発する。ネオリベラリズムが生み出した構造的な社会問題を都市論の代表的論客M・デイヴィスが読み解く。
目次
第1章 都市の転換期
第2章 スラムの拡大
第3章 国家の背信
第4章 自立という幻想
第5章 熱帯のオースマン
第6章 スラムの生態学
第7章 第三世界を構造調節する=搾り取る
第8章 過剰人類?
エピローグ ベトナム通りを下って
著者等紹介
デイヴィス,マイク[デイヴィス,マイク][Davis,Mike]
1946年カリフォルニア州フォンタナ生まれ。精肉工場の工員やトラック運転手、SDSの活動家といった経歴の持ち主。リード大学で歴史学を学んだあとUCLAに進むが学位をとっていなかったために教職につかない時代を長く過ごした。南カリフォルニア大学建築学部とカリフォルニア大学アーヴァイン校歴史学部を経て現在はカリフォルニア大学リバーサイド校クリエイティブ・ライティング学科の教授。『ニューレフトレヴュー』誌の編集委員でもある
酒井隆史[サカイタカシ]
大阪府立大学准教授
篠原雅武[シノハラマサタケ]
日本学術振興会特別研究員(PD)。1975年生まれ
丸山里美[マルヤマサトミ]
立命館大学産業社会学部准教授(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
yooou
3
☆☆☆☆★ 目を覆うばかりのスラムの現状と照らし出される来るべき将来のメガシティのおぞましい姿。圧倒的な暴力にさいなまれているスラムの子供達には激しく心が痛みました。なんとかしなければ、これに対して僕達のできることは何かを真剣に考えさせられる本でした。 2011/09/15
Mealla0v0
2
訳者解説にあるように、本書で示されたスラムは第三世界に固有のものなのではなく、スラム化という現象の帰結であり、それは先進国とも無縁ではない。相当数の事例が煩雑にも思えるが、スラムが過剰人類を収容する、国家から放擲されたゾーンであるという指摘は、都市のダーティな部分を想起させる点で興味深い。貧者間の格差拡大、生存資源の商品化などネオリベ化による貧困化が描かれている点は、アンダークラスの議論とも重なる。公衆衛生の問題に関連して、ある意味で、生政治の出生地である都市の権力作用を考えるべきだと思う。2018/03/05
大菩薩
2
発展途上国におけるスラム化と貧困についての『告発』に近い本。都市のスラム化と貧困の再生産を、IMF、世界銀行、先進諸国と途上国のエリートたちによる『犯罪』であるとまで指摘する。スラム化に関するデータから始まり、IMFや先進国によってどのようにスラムが『造られて』いくかを検証したうえで、後半部ではスラムで今何が起こっているかを記述する。途上国のスラムの有様は一種のおぞましさを感じさせるほどである。少し描写に思想的な偏りが感じられるため鵜呑みにするのは危険かと思われるが、非常に興味深い内容だった。2011/03/03
ピリカ・ラザンギ
1
スラムの発生と経済、国家のスラム(貧者)を自立させる政策が実際は富裕層や中間層へ資金が行くようになっている例や、美化や経済的発展のための名の下にスラムを破壊することの例。グローバリゼーションとネオ・リベラルな政策が貧民から生きる方法を奪っていくこと。スラムに住む人間がほとんど無視(社会保障などのサービスの外)されていることなど。日本では地方が縮小しているが都市は人口増(これは本書でも同じ)だが、人口減であり都市もスポンジ状に人口が減っていくという。そこに貧困が加わった場合はどうなるのだろうか?2017/12/25
まつゆう
1
ここでのスラムを告発する内容をまた第三世界の話と、他人事としてはいけない。日本では形を変えて、例えば、ワーキングプアやホームレスの問題として類似の問題が起こっていると見るべきだろう。2016/02/05