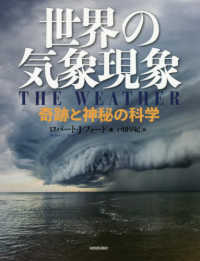出版社内容情報
学校の安全をどう守るのか? OECDとアメリカ教育省による教育施設プログラム(PEB)の報告書であり、大阪・池田小学校の事件やフランスの化学工場爆発事故をはじめ、世界各地で実際に起こった「学校の危機」とそれに対する取り組みを分析・評価し、これからの「学校の安全」のあり方を提示する。
日本版序文
序文
概要
第1部 リスク・アセスメント
第1章 オーストラリアの後期中等教育制度におけるリスク分析手法の展開
第2章 フランスの学校におけるリスク・アセスメント
第3章 韓国の学校安全調査
第2部 危機管理の計画とマネジメント
第4章 日本における学校安全のアプローチ
第5章 ニューヨーク市における危機管理計画
第3部 インフラ面の整備
第6章 アイルランドの学校設計における安全の見直し
第7章 ギリシャにおける学校施設の安全
第8章 より安全な学校をめざすイギリスのプロジェクト
第9章 自然災害に対するメキシコ教育部局の行動計画
第4部 協働的アプローチ
第10章 国際的視点からの学校安全への総合的アプローチ
第11章 カナダにみる安全と配慮ある学習コミュニティの創造――「ともに道を照らそう」
第12章 マレーシアにおける学校安全プログラム設立のための戦略的な3者間連合
第13章 ビジョナリー――学校の暴力防止に関する欧州の国際的なインターネットポータルサイト
第14章 校内暴力――欧州の展望
第5部 教育、訓練そして支援
日本語版序文
本書は、OECD(経済協力開発機構)が2005年に刊行したLessons in Dangerの全訳である。直訳すると「危機のレッスン」だが、「危機に学ぶこと」というのがその意だろう。ただし、本書の副題には「School Safety and Security」があり、学校をめぐる安全対策が本書の内容なので、邦題も「学校の安全と危機管理」とした。しかし、本書を読んでいただければ、学校の安全を守り、子どもたちの命を守るには、まず市民全体の命と生活が保障される必要があり、そのためには、私たちが学校をめぐる危機から多くを学ぶ必要がある、ということの重要性も浮かび上がってくる。
私たちが学校の危機から何を学び、学んだ知識や技術をどのように教育や行政、そして広くは市民生活に活用するかについて、本書は多くの国々の例を示しながら問いかけてくる。
実際、本書で取り扱われた例に加えて、2004年12月にはインドネシア・スマトラ島沖地震が発生し、その津波は多数の沿岸諸国に被害を及ぼし、23万人以上の死者をもたらした。2005年8月には米国を大型ハリケーン「カトリーナ」が襲い、アラバマ州、ミシシッピー州やルイジアナ州が大きな被害にあい、特にニューオリンう言葉が示すようにもともと安全な場所だったのだろうか? そこは、人間や社会が自らの意図的な努力でもって、安全な場所にしていくことが求められる場所なのではないだろうか? 地球の温暖化に伴う大型台風の発生件数増加、国際紛争の地域化や殺傷力の増大した武器使用、麻薬の普及などによる人為的被害の拡大など学校は多くの脅威にさらされ、その安全を守ること、つまり安全な環境で子どもたちの成長を保障するという権利を守るためには、いっそう優れた対策や計画を政府や専門家、そして市民がともに考え、実行することが求められる時代になってきた。
学校を守ることとは子どもたちの生命と未来を守ること、それは同時に国民や市民の教育機会を保障し、社会の未来を保障することを意味する。つまり、どの国にとっても、学校の安全は、教育の最優先課題なのである。学校の安全を確保し保障するためには学校教員はいうに及ばず、警察や運輸、医療などの行政各部局に加えて、建築家、危機管理コンサルタント、心理学者や社会学者などの専門家の協力、さらには地域住民の自主的協力が不可欠となる。
本書は、そうした視点に立って行われたOECDと米国教育省の協働事業の成果であり、緊急事究が進んでいるかという問題がある。日本では、いじめや虐待といった問題への研究は進んでいても、防犯対策や防災学習の研究がどれほど進んでいるのだろうか。各国ごとに研究への取り組み状況に大きな差異があることも本書からわかる。安全対策の現状を見ると、それぞれの国が受けた被害や事件が中心となり、学校の安全という広く長期的な視点で、多様な問題の要因や安全を脅かす傾向を分析し、総合的な取り組みを取ること自体が難しいことを本書は指摘している。しかし、学校の危機管理をめぐる多様な問題に世界が協働で取り組み、その知識や技術の共有化を図る必要のあることも事実である。
いくつかの章では、危機管理対策を行うための理論的な枠組みや実証的な分析の重要性を述べている。たとえば、枠組みの一つに、危機の分類がある。台風、地震、山火事などの自然災害だけでなく、人為的災害にもきわめて多様なものがある。テロ、停電、殺人、放火、破壊、窃盗などの犯罪や暴力事件だけではなく、エイズ・薬物・アルコール問題や科学技術による災害がある。また、多文化・多民族問題、いじめや校内暴力など心理・社会的問題が引き起こす危機もある。
さらに、自然と人為という分類だけている。
本書の特に優れた点は、運営面における多様な支援や工夫が紹介されていることだろう。
国際的な協働、地域と学校の協働事例などの「制度的工夫」、災害救済機構や公的施設への「財政的支援」、監視カメラやインターネットなどの「安全のための技術開発」、教育面ではモデル校の実験や反社会的行動、校内暴力の防止などのプログラム開発、そして危機管理ツールや手順書を含む「防災や防犯のためのプログラムや教材とマニュアルの開発」である。
最後にまとめられている教職員や児童・生徒への訓練や教育、専門家養成プログラムなどの「防災教育と専門的人材の養成」は、日本でも今後いっそう力を入れて取り組まれる必要がある支援策だろう。学校の構成員である生徒や教員が自ら身を守る知識と技術を身につけることは、防災学習の初歩だろうし、同時に学校の安全を守る専門家の養成を行うことがさらに求められるだろう。実際、日本でも平成17年度より地域学校安全指導員(スクールガード・リーダー)の育成と配置が始まるという。その成果を期待したい。
本書の翻訳にあたっては、安藤友紀さんが全訳を行い、立田が全文の推敲を行った。第4章については、元文部科学
目次
第1部 リスク・アセスメント(オーストラリアの後期中等教育制度におけるリスク分析手法の展開;フランスの学校におけるリスク・アセスメント ほか)
第2部 危機管理の計画とマネジメント(日本における学校安全のアプローチ;ニューヨーク市における危機管理計画)
第3部 インフラ面の整備(アイルランドの学校設計における安全の見直し;ギリシャにおける学校施設の安全 ほか)
第4部 協働的アプローチ(国際的視点からの学校安全への総合的アプローチ;カナダにみる安全と配慮ある学習コミュニティの創造―「ともに道を照らそう」 ほか)
第5部 教育、訓練そして支援(オーストラリアにおける学校危機管理のための教育と訓練;アルメニアの非常事態に対応する児童・生徒の訓練 ほか)
著者等紹介
立田慶裕[タツタヨシヒロ]
1953年生まれ。大阪大学大学院人間科学研究科後期課程単位取得退学。現在、国立教育政策研究所・総括研究官
安藤友紀[アンドウユキ]
1974年生まれ。早稲田大学第一文学部英文学専修卒業。現在、NPO法人キャリア・ワールド事務局長。防災教育・防犯教育の開発、実践、普及に努める(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。