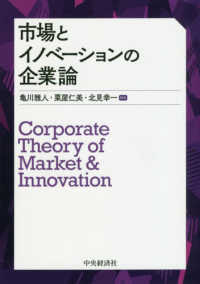出版社内容情報
養子となった子どもに、養子となること、養子であることの意味を教えるための絵本。1978年にアメリカで刊行。子どもだけでなく、里親にとっても「告知」にあたっての基本的な考え方を知るのに役立つ。養子や里子と接する人たちにぜひ一読してほしい良書。
この本は、養子の子どもに養親(育ての親)が「自分たちは血のつながりのない親子である」ことを伝える、いわゆる「真実告知」の問題を、絵本というかたちで述べたものです。
ごくふつうの親子であると思っていた子どもにとって、血のつながった親子ではないことを知らされるのは、また親だと思っていたのは「育ての親」で、「生みの親」は別の人であることを知らされるのは、まさに青天の霹靂といえるでしょう。
いったいなぜそんなことになったのか? なぜ親はこのことを私に言ったのか? 生んでくれた親(原書では「いのちをくれた人」となっています)はどんな人だったのだろうか? そもそも養子縁組って何?
子どもが感じるであろうこれらの問いへの答え(あるいは考え方)を述べることが本書の目的です。子どもにとってもっとも重大な問題を、著者は、考え方のポイントはしっかり押さえ、しかもユーモアをまじえ、思いやり深い態度で述べています。
本書には養子縁組制度についての説明もありますが、これはアメリカのことで、わが国の制度とはちがうこところもあります。しかし、趣旨を理解するうえでとくに支障はないと考え、そのまま訳出してあります。あとがきの最br>
私はこの本を1990年にオーストラリアを訪れたときに書店で見つけ、買い求めました。その後、アメリカでも買いました。というのは判型がやや小さくなっていたからです。あとで読み比べてみると、具体的な例を示すところがいくつか異なっていました。アメリカ版が原本であることがわかったので、これを翻訳の底本としました。本書の原本は1978年に出版され、今日でも版を重ねており、スペイン、スウェーデンでも翻訳されているということです。
残念ながら、著者や作画をした方については情報が得られませんでした。しかし、彼らは、本書が含まれるシリーズの他の本にもかかわっています。
翻訳にあたって、絵本であること、若い読者がいることを考え、小学校低学年で学ぶレベルの漢字を使用し、また漢字にはすべてルビをふりました(このあとがきは、大人の方を対象に書いています)。本書は、養親(里親)が読んで、告知をするときの心構えをつくるのにも役立つのではないでしょうか。また、養子に限らず、里親のもとで生活している子ども、親と別れて施設で生活している子どもにも当てはめて考えることができると思われます。また、多くの方に読んでいただき、生まれた家庭で
内容説明
養子となった子どもに、養子となること、養子であることの意味を説明するために著された絵本。子ども向けの本だが、むしろ、里親にとって、「告知」にあたっての基本的な考え方を知るのに役立つ。養子や里子と接する親たちにぜひ一読してほしい良書。
著者等紹介
庄司順一[ショウジジュンイチ]
1949年東京都に生まれる。1975年早稲田大学大学院文学研究科心理学専攻修士課程を修了。同年東京都職員(心理技術職)となり、1979年より都立母子保健院心理指導員。1992年恩賜財団母子愛育会日本総合愛育研究所(現日本子ども家庭総合研究所)主任研究員。94年企画室長、97年研究企画・情報部長。1999年青山学院大学文学部教育学科教授、現在にいたる。日本子ども家庭総合研究所福祉臨床担当部長(非常勤)。1983年川崎市にて里親登録。専門は臨床保育学、子ども虐待、里親養育、乳児院での養育
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
さおり
ヒラP@ehon.gohon
Sayaka
maaaa