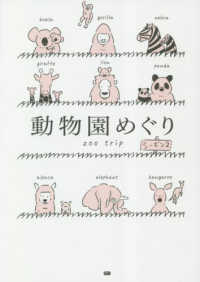内容説明
藤原氏による摂関政治が確立していく中、道真はそれとどう向き合い、やがて「敗者」として太宰府に流されるのか。道真が残した漢詩を読み解きつつ、「詩臣」としての行跡と、道真を「敗者」とした摂関政治の成立を探る。
目次
菅原道真とその時代―プロローグ
1 祖業は儒林 聳えたり―「詩臣」の形成
2 吏と為り儒と為りて国家に報じん―讃岐守時代
3 藤氏の勲功 勒みて金石に在り―摂関政治の成立
4 恩沢の身を繞りて来る―国政を担う
5 万事皆夢の如し―大宰府流謫
道真とその時代が残したもの―エピローグ
著者等紹介
今正秀[コンマサヒデ]
1963年兵庫県出身。1985年広島大学文学部史学科卒業。1992年広島大学大学院文学研究科博士課程後期単位取得退学。現在、奈良教育大学准教授(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
Tom
4
2013年刊。菅原道真の研究書は戦前の昔からたくさん出ているので、その中で考えると新しいほう。道真と言えば、学問で身を立て出世するが、藤原氏に目を付けられて讒言により左遷された、という”通説”が有名である。道真の生涯を軸に、崩壊しつつある律令制度、そして変革を迫られる国司制度、基経、時平ら藤原北家との関係、太宰府左遷の真相について迫っている。→2023/10/07
MrO
4
実証的な研究はわかるんだが、通説や陰謀説が資料によって見直されていった先が、結局モヤッとしてなんとも言えないという感想しか持てない。2022/02/11
wang
4
藤原氏との権力対立に破れて太宰府に左遷され祟神となった位しか知らなかった道真公。詩作の家に生まれた彼がどのように最高権力へと駆け上ったのかの過程から描かれている。個人的には先日読んだ郡司の末期、国司支配が崩れ受領化する頃に讃岐国司として下り地方支配を経験したあたりの記述がタイムリーで面白かった。摂政・関白の成立や初期の意義あり方などを延べた部分も初見の内容が多く勉強になった。詩臣たりたかった道真が天皇に寵愛されたばかりに権力を得て陥れられる結果となる。悲哀を感じる。2013/12/19
キングトータス
3
制度的な部分は難しく充分に理解出来なかったので再読したい。今回学んだ事は、まず道真は儒者・詩人としての自負が強く、最初の讃岐への赴任は必ずしも左遷というわけではなく、中央で「詩臣」としての勤めを果たせない事を不本意としていただけで任地での仕事は真面目にこなしていた事。次に藤原時平との関係は特に悪くなく、太宰府への左遷は時平の讒言が原因ではない事。しかしだとするとなぜ醍醐天皇は道真を排除したのだろうか?他の本も読んでみたい。2022/04/13
マウンテンゴリラ
3
図書館で面白そうな歴史シリーズ本を見つけ、全20巻を読了してみようと思い立った。時代は前後するが、まず最初に目に止まったのは、歴史における陰謀の犠牲者として、その代表のように扱われ、今では文治政治の英雄とされている感さえある菅原道真であった。そのあまりな人気ぶりから、氏を陰謀を持って政治の舞台から追いやったとされる、藤原一族とその後築かれた摂関政治そのものが、悪の権化のようにさえ見なされ、少なからず私もそのような認識を持っていたのも事実である。しかし、歴史の事実やその解釈は日々更新され、→(2)2021/10/20
-
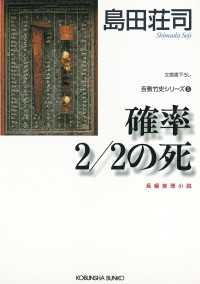
- 電子書籍
- 確率2/2の死~吉敷竹史シリーズ5~ …