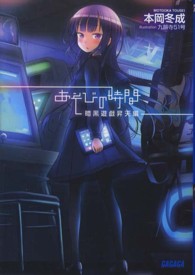内容説明
時代劇や小説に登場するさまざまな刑罰。江戸小伝馬町の牢屋、火附盗賊改長谷川平蔵の建議で設置された人足寄場の実態は、果たしてどうであったか。日本法制史の研究成果をふまえ、実証的にわかりやすく叙述した名著。
目次
吟味から落着まで
1 御仕置(鈴ヶ森の露―生命刑;額に悪の文字―身体刑;八丈島送り―自由刑;とりああげの刑―財産刑、身分刑、栄誉刑)
2 牢屋(“小伝馬町”の塀の中;格子の中の暮し;シャバと牢屋;溜)
3 人足寄場(佐渡の水替人足;無宿者収容所;油絞りのノルマ;水玉人足の生活;寄場から徒刑場へ)
著者等紹介
石井良助[イシイリョウスケ]
1907年東京市に生まれる。1930年東京帝国大学法学部法律学科卒業。東京大学教授、新潟大学教授、専修大学教授、創価大学教授を歴任。1990年文化勲章受章。1993年没(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
マカロニ マカロン
11
個人の感想です:B。来月の聖地巡礼「江戸市中引き回しの上、張りつけ獄門」の参考本。小伝馬町の牢屋跡スタートで南千住小塚原の回向院までのコースだが、江戸時代の「市中引き回し」が正式には「五箇所引廻」でえらく長い行程なのだと知った。本書には色んな生命刑のやり方が詳細に書かれていたが、それよりも恐ろしく感じたのは「大牢」のなかでの「牢内役人(牢名主など)」によるマウンディングのための儀式、金蔓を持ってこなかったものへのリンチなどの記述だ。江戸時代の牢屋は未決囚の拘置所だというが、被疑者=有罪という決め付けは怖い2022/03/28
ぼのまり
1
江戸時代の牢屋の仕組みや日常、刑罰の仕組みについて解説した本。「大岡越前」や「遠山の金さん」などの時代劇のような裁きがされていたわけではないのですね。勉強になります。2013/05/06
なかのっこ
0
内容が内容だけに追体験したような痛みを感じた。絶対に悪いことしないし牢屋に入りたくないし、関わりたくない。2018/04/21
-
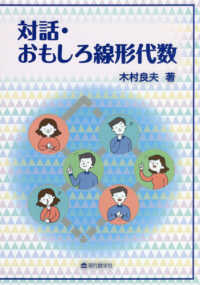
- 和書
- 対話・おもしろ線形代数