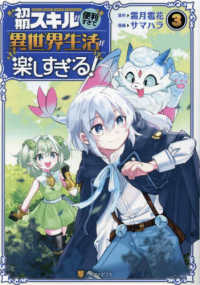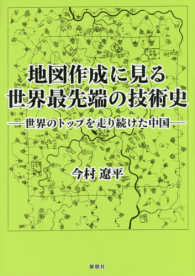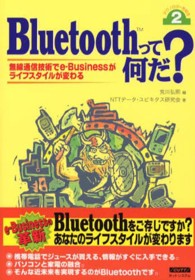出版社内容情報
『平家物語』を中心に、富士川から壇ノ浦までを詳述。軍事制度の変遷、武人としてのあり方の違い、後白河院の関与などから描く。源義経らの活躍で源氏が勝利し、鎌倉幕府の成立史として語られる源平合戦を、敗れた平氏の視点から描くと何が見えてくるのか。『平家物語』を中心に、富士川から壇ノ浦にいたる経過を、在地勢力の動向とそれら集団のもつ性質を解き明かしつつ詳述。軍事制度の変遷、武人としてのあり方の違い、後白河院の関与、戦争目的の変化など、多方面から描く。
平氏からみた治承寿永の内乱―プロローグ/東国の喪失(勝算なき富士川の戦い〈頼朝・義仲の挙兵/儀礼となった追討使派遣/苦難の旅となった東国下向/甲斐源氏の攻勢/富士川合戦の虚実/壊走〉以下細目略/近江・美濃の消耗戦/養和元年の北陸合戦)/平氏都落ち(北陸道の喪失/七月二十五日/それぞれの都落ち)/一ノ谷合戦(西海での勢力回復/生田の森の戦い/悲劇となった浜の戦い)/屋島・壇ノ浦の合戦(山陽道の戦い/屋島の戦い/壇ノ浦の戦い)/平氏の人々が遺したものとは―エピローグ/治承寿永の内乱年表
永井 晋[ナガイ ススム]
著・文・その他
内容説明
源平合戦を敗れた平氏の視点で描くと、何が見えてくるか。『平家物語』を中心に、富士川から壇ノ浦までの経過を詳述。軍事制度の変遷、武人としてのあり方の違い、後白河院の関与、戦争目的の変化など、多方面から描く。
目次
平氏からみた治承寿永の内乱―プロローグ
東国の喪失(勝算なき富士川の戦い;近江・美濃の消耗戦 ほか)
平氏都落ち(北陸道の喪失;七月二十五日 ほか)
一ノ谷合戦(西海での勢力回復;生田の森の戦い ほか)
屋島・壇ノ浦の合戦(山陽道の戦い;屋島の戦い ほか)
平氏の人々が遺したものとは―エピローグ
著者等紹介
永井晋[ナガイススム]
1959年、群馬県に生まれる。1986年、國學院大学大学院博士課程後期中退。神奈川県立金沢文庫主任学芸員・神奈川県立歴史博物館企画普及課長を経て、関東学院大学客員教授、博士(歴史学)(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ブックウォーカーの提供する「読書メーター」によるものです。
ようはん
ゆの字
うしうし
餅屋
onepei