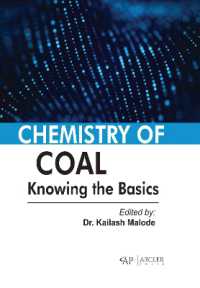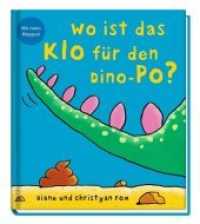出版社内容情報
★大好評 緊急重版決定!
内容説明
長屋王、菅原道真、崇徳院…。非業の死を遂げ、祟りや災いを起こした怨霊は、為政者により丁寧に祀られた。虚実とりまぜて論じられがちな怨霊の創出と鎮魂の実態を実際の史料に基づいて辿り、怨霊を時代の中に位置づける。
目次
怨霊とは何か―プロローグ
怨霊の「誕生」と初期の怨霊
怨霊の大衆化
跋扈する怨霊
怨霊の「終焉」
怨霊を通して見えるもの―エピローグ
著者等紹介
山田雄司[ヤマダユウジ]
1967年、静岡県に生まれる。1991年、京都大学文学部史学科卒業。1998年、筑波大学大学院博士課程歴史・人類学研究科史学専攻(日本文化研究学際カリキュラム)修了、博士(学術)。三重大学人文学部准教授(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
皆様の「暮らし」を応援サポート
17
上代日本でやらかしまくった天皇家と藤原氏はその都度怨霊を生み出しては鎮めていくが、道真あたりから怨霊の大衆化は防げなくなっていき、また乱世に入るなかで後白河院の神仏祈祷は怨霊発生とのいたちごっこ状態に陥る。頼朝はそれを転倒させ、過去の敗者=怨霊や死者を鎮魂し、英霊化させることで規範として利用する。室町時代以降になると怨霊はキャラクター化されコンテンツ化していくなかでその力を失っていく。後半の怨親平等論は展開の仕方がやや危うい気がした。個人的には志多良神入京事件と愛宕山怨霊オールスターズが面白かった。2021/12/24
テツ
16
世界を、社会を、敵対したこの自分を怨みながら死んでいった(と自分が思い込んでいる)既に存在しない相手に怨霊という人格を与えることで、相手のきもちなど全く関係なく一方的に赦しを請えるし、崇め奉れば赦しどころか自分たちを守ってくれる存在にまで昇華できる。決して最初から論理的に構築された訳ではないのだろうけれど良くできたシステムだなと感心する。存在しなくなった相手に対する罪悪感を薄めるために敢えて怨霊という形でこの世界に繋ぎ止める。謝罪も逆ギレも相手がいなければできないもんな。斯くしてこの世には怨霊が跋扈する。2022/02/08
Toska
15
読みやすく分かりやすい怨霊の通史。真面目に怨霊を恐れていた当時の人々の心性に向き合い、一方で社会的・政治的な背景にも目が配られ、よくバランスが取れている。登場する怨霊の中では後鳥羽院の暴れん坊ぶりが印象的だが、世間的にはやっぱり崇徳院の方が有名なのだなあ。これは保元の乱が武者の世の台頭を招いた歴史的な転換点であり、倒幕が課題となった明治期に「崇徳院の怨霊」が思い出されたから、という説明に説得力を感じた。2024/10/08
遊未
7
怨霊というと平安時代までを思ってしまいますが、太平記の時代まで取り扱いがあり、有名どころが揃っています。次第に民衆的となり、鎮魂の対象となります。初めてだったのは護良親王で、先頭に立って活動したけれど、政治的な立ち回りには向かなかった方でしょう。怨霊とならない方が不思議なほどの壮絶な最期でした。2022/03/20
らむだ
5
古代から中世にかけての怨霊の「誕生」から「終焉」までを資料に沿って辿る一冊。本書で取り扱う怨霊は政治の中枢部に現れたものに限られている。2022/12/29