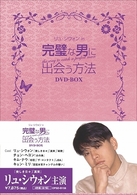内容説明
内憂外患の中で、儒学倫理をもとに「世界の中の日本」を構想し、近代化の論策を編み出した政治思想家。松平春岳・橋本左内・坂本竜馬らとの交遊を交え、非業の最期に至る波瀾の生涯を、幕末社会にダイナミックに描く。
目次
実学への取り組み
福井藩へ
幕政改革に意欲
維新政府へ
近代日本への啓発力
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
1.3manen
26
学問とは己を修めることで、書を読み独り自ら修養するのを真の儒者といい、経を講じ、史を談じ、文詩に達する人を学者という(61頁)。小楠は当時の主流だった朱子学を究めるほど、内憂外患の政治社会に対処できぬと考えた。朱子学を基底に、仁政の本源的な儒教倫理に根ざした理想社会をめざしていた(198頁)。心徳=至誠の惻怛(そくだつ)の倫理性にもとづく経世済民論がかかげられた。徳は本なり、財は末なり(中国の古典『大学』)。道徳主体で経済は追従するとした(199頁)。2016/01/29
mi ya
0
小楠の思想よりも生涯や背景を主とした著作。他の小楠の思想本を読んだ上で取りかかると更なる深みが味わえる。
-
![私たちの社会福祉は可能か[固定版面]](../images/goods/ar2/web/eimgdata/EK-2049193.jpg)
- 電子書籍
- 私たちの社会福祉は可能か[固定版面]