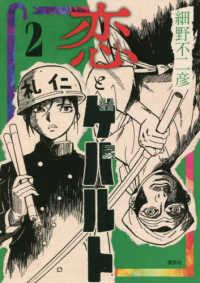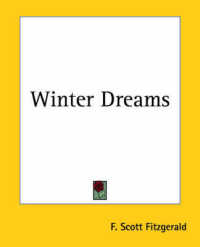内容説明
“普通の人々”が国家のために殺し殺される徴兵制は、どう受け入れられたのか。徴兵制維持のサブ・システム=「軍隊教育」と「軍事救護」を分析。戦争自体をも正当化する論理がいかに語られていったのかを解き明かす。
目次
第1部 兵士が軍隊生活の「所感」を書くこと―軍隊教育の一側面(日露戦後の兵士「日記」にみる軍隊教育とその意義;「大正デモクラシー」期における兵士の軍隊生活「所感」)
第2部 軍事救護制度の展開と兵役税導入論(日露戦後の兵役税導入論と軍事救護法;第一次大戦後の陸軍と兵役税導入論;「護国共済組合」構想の形成と展開)
第3部 地域社会と軍事援護―日中戦争期以降における(軍事援護と銃後奉公会;戦死者遺族と村―太平洋戦争期における;兵士の死と地域社会)
著者等紹介
一ノ瀬俊也[イチノセトシヤ]
1971年福岡県に生まれる。1998年九州大学大学院比較社会文化研究科博士後期課程中退。現在、人間文化研究機構国立歴史民俗博物館助手、博士(比較社会文化)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ブックウォーカーの提供する「読書メーター」によるものです。
Toska
9
徴兵制を支えた諸々のシステムの分析。第一部で軍隊教育、二部・三部では兵士やその遺家族、傷痍軍人に対する支援(「軍事援護」)が取り上げられている。日本軍の新兵教育は、単に軍人としての能力を高めるにとどまらない全人格的な陶冶を目指す、所謂「良兵良民」思想に特色がある。このような教育思想も、結果として悪名高い日本軍の精神主義をもたらす一因となったのではないかと感じた。2023/07/10
金吾
5
以前より興味のある題材でしたので、一気に読めると思いきや時間がかかりました。制度について詳しく書いており、特に第一次世界大戦後の陸軍内における議論は面白かったです。2020/03/21