出版社内容情報
地中海沿岸のイタリア半島から日本海の対馬に及ぶユーラシアの東西で、さまざまな危機が生じていた1861年。打開の道はどこにあるのか。試練のときを生きた人びとの胸のうちと行動に迫る。
小松 久男[コマツ ヒサオ]
編集
内容説明
異国船の来航、岐路に立たされた改革、国家の存亡、国民の統合。ユーラシア大陸の東西で生じたさまざまな危機のなかで打開の道を模索した人びとの胸の内と行動を追う。
目次
総論 改革と試練のなかの一八六一年
1章 危機のなかの清朝
2章 岐路に立つタンズィマート
3章 陸軍大臣ミリューチンの回想
4章 ポサドニック号事件の衝撃
5章 イタリア統一と移民
著者等紹介
小松久男[コマツヒサオ]
1951年生まれ。東京大学大学院人文科学研究科博士課程中退。専攻、中央アジア近現代史。東京外国語大学特別教授、東京大学名誉教授(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
1 ~ 1件/全1件
- 評価
-





akky本棚
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
MUNEKAZ
11
英露のグレート・ゲームの真っ只中、生き残りをかけて体制変革に挑んだ清・オスマン・ロシアの官僚たちや、大国の狭間で翻弄される日本の姿を描いた章が印象的。とくに三帝国の改革は、その後の結末から「無駄」だったと思われやすいが、それでもこの改革があったからこそ、この後150年近くも国家の命脈を保てたのだろうし、彼らの苦闘にも意味があるのだろう。また、複数の論にまたがって登場するロシアの外交官イグナチェフの黒幕っぷりもなかなかであった。他にも番外編的にあるリソルジメント後のイタリア移民たちの相貌も興味深い。2018/11/08
ピオリーヌ
8
清朝・オスマン帝国・ロシア帝国・日本・イタリアが取り上げられる。対馬・沿海州・バルカン半島・中央アジアで何れも大きな役割を果たす、ロシア帝国の存在感が印象的。1861年、対馬にロシア軍艦が来航し、半年に渡って海岸を占拠したポサドニック号事件は寡聞にして知らなかったが、当時の日本にとって多大なインパクトを与えた事件と言える。英露の世界史的対立が日本海に持ち込まれ、また自らの力量でそれを解決できなかった(イギリスを通してロシアに抗議を行った)日本の非力さが記憶に残る。2021/11/03
みいしゃ
0
なんで南北戦争を入れてくれなかったんだろう?2019/05/24
-
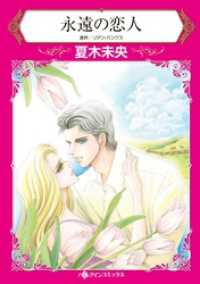
- 電子書籍
- 永遠の恋人【分冊】 6巻 ハーレクイン…
-

- 電子書籍
- 法学教室2022年3月号 法学教室







