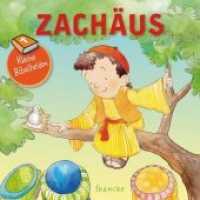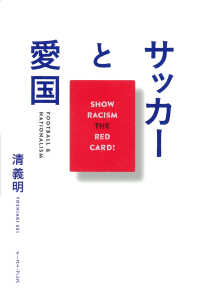出版社内容情報
これまで民俗学は普通の人びとの生活世界を把捉しようと〈語り〉にこだわってきたが、近年ナラティヴ、語り、物語、オーラリティーは実践的な概念としてさまざまな領域でとりあげられるようになっている。本書はドイツ民俗学における第一人者であるアルブレヒト・レーマンの来日を機縁として〈語り〉に注目するさまざまな分野の日本の研究者が論考を寄せ、その重要性を問い直した一冊である。
内容説明
これまで民俗学は普通の人びとの生活世界を把捉しようと“語り”にこだわってきたが、近年ナラティヴ、語り、物語、オーラリティは実践的な概念としてさまざまな領域でとりあげられるようになっている。本書はドイツ民俗学における第一人者であるアルブレヒト・レーマンの来日を機縁として“語り”に注目するさまざまな分野の日本の研究者が論考を寄せ、その重要性の問い直しを目論むものである。
目次
ナラティヴと主観性の復権―民俗学からの問い
第1部 なぜ“語り”研究なのか(民俗学の方法としての意識分析;ドイツにおける日常の語り研究の系譜;カタリとハナシ―世間話研究の展開;神秘化された森と環境保護運動―ドイツの事例より)
第2部 意識分析とナラティヴ(気分と雰囲気―意識分析のコンテクストにおける記憶と語りに及ぼす影響;“意識分析”がもたらす革新―社会福祉研究の立場から;民族誌的研究とナラティヴ―対話のパフォーマティヴィティ;意識分析における「語り」と「記憶」の位置)
第3部 オーラル・ヒストリーと語りのアーカイヴ化(意識分析とオーラル・ヒストリー―オーラルナレーションのアーカイヴ化;社会学における質的データとアーカイヴ化の問題―オーラリティと声の公開の可能性;歴史研究のなかの「記録」;ライフ・ストーリーと民俗学)
著者等紹介
岩本通弥[イワモトミチヤ]
1956年東京都生まれ。1986年筑波大学大学院博士課程歴史・人類学研究科満期退学、修士(文学)。現在、東京大学大学院総合文化研究科教授(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
-

- 電子書籍
- 将棋パワーアップシリーズ この局面は詰…