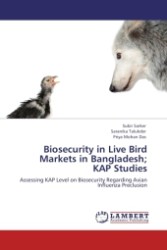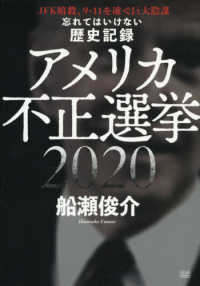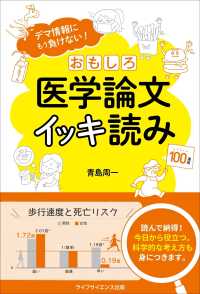出版社内容情報
「帝国」日本における共同社会のあり方とは…… 普遍と固有を問い続けた大正知識人の思索。「大正デモクラシー」の学問といえば柳田民俗学がその象徴とされてきたが、吉野作造の明治文化研究も在野性や反権力性が論じられてきた。本書では、吉野の「民本主義」論、東アジア論の全体から明治文化研究を読みなおし、その学問の本質を明らかにする。また柳田の思想をキリスト教精神、アカデミズム、政治という観点から再検討し、両者の学問に通じる第一次世界大戦のインパクト、普遍性への希求という特徴を明らかにする。
はしがき
序 章 吉野作造と柳田国男の比較研究
1 吉野と柳田の思想比較
2 研究の対象時期とテーマ・時期区分
第?部 「大正デモクラシー」と宗教精神
第一章 吉野作造における「国体」と「神社問題」??キリスト教精神の普遍化と国家神道批判
1 「内面的権威」と「服従」
2 キリスト教と国家との対立・調和
3 「国体」の普遍的基礎としての宗教精神
4 神社問題に対する批判
5 普遍的で合理的な「道徳」による「国体」の改造
第二章 柳田国男における民間「神道」観の成立とキリスト教??「国民倫理」形成と神社合祀政策批判
1 民間「神道」研究への道のり
2 キリスト教と「幽冥教」の狭間で
3 山人の実在と境の神信仰の探求
4 民間「神道」発見におけるキリスト教の役割
第三章 柳田国男における「固有信仰」と「世界民俗学」??キリスト教との関連から
1 「母子神」と聖母マリア
2 「固有信仰」とJ・G・フレイザー??「母子神」信仰を中心に
3 『桃太郎の誕生』とキリスト教
4 日本の「固有信仰」の特徴と「世界民俗学」
5 「固有信仰」とキリスト教
第?部 現実の政治認識と学説
第四章 1920年代の柳田と吉野の政治思想??「共同団結の自治」と「政治的自由」
1 「大正デモクラット」の共通点と相違点
2 植民地統治政策および移民政策批判
3 「国民総体の幸福」と「国民の自由」
4 両者における「政治」
第五章 「デモクラシー」と「生存権」??吉野作造と福田徳三との思想的交錯
1 「経済的デモクラシー」をめぐって
2 黎明会以前
3 第一次世界大戦観および「ソーシャル・デモクラシー」をめぐる論争
4 吉野・福田の思想的交錯
5 黎明会解散後
6 「自由」と「自決」のデモクラシー
第六章 「共同団結の自治」実現への模索??「民俗」の価値および神道政策への提言
1 「民俗」と民主国家及び戦争
2 普選と産業組合における「親方制度」の影響
3 口語教育による「民主主義」育成
4 大政翼賛会と柳田民俗学
5 無格社整理問題に対する筧克彦意見と柳田
6 「共同団結の自治」実現のための政策の提唱
第七章 吉野作造の「現代」政治史研究??政治史講義を中心に
1 「明治文化研究」の再検討
2 社会変革思想としての「民本主義」
3 中国革命史研究から日中関係の展望へ
4 明治維新期の民間世論と立憲君主制
5 尾佐竹猛『維新前後に於ける立憲思想の研究』との比較
6 「民本主義」の世界史的展開の構想
第八章 「郷土研究」とアカデミズム史学??「神話」研究の再興及び歴史資料論
1 柳田民俗学とアカデミズムの関係再考
2 久米邦武事件後の記紀神話・民間信仰研究
3 歴史資料論における「郷土研究」とアカデミズム史学
4 中世史開拓における協同と「伝説」の史的価値をめぐる対立
終 章 「大正デモクラシー」の学問の特徴
1 キリスト教・「帝国」日本・歴史
2 「大正デモクラシー」の学問の特徴と現代
補 章 「新しい歴史学」と「我々の文化史学」
1 「文化史」=歴史学界の新潮流
2 『史学雑誌』・『史林』・『史学』彙報欄の「民俗学」
3 「新しい歴史学」と柳田国男
4 実証主義に基づく国民「文化史」の構築
注
主要参考文献
あとがき
事項索引
人名索引
田澤 晴子[タザワ ハルコ]
著・文・その他
内容説明
「大正デモクラシー」の学問といえば柳田民俗学がその象徴とされてきたが、吉野作造の明治文化研究も在野性や反権力性が論じられてきた。本書では、吉野の「民本主義」論、東アジア論の全体から明治文化研究を読みなおし、その学問の本質を明らかにする。また柳田国男の思想をキリスト教精神、アカデミズム、政治という観点から再検討し、両者の学問に通じる第一次世界大戦のインパクト、普遍性への希求という特徴を明らかにする。
目次
吉野作造と柳田国男の比較研究
第1部 「大正デモクラシー」と宗教精神(吉野作造における「国体」と「神社問題」―キリスト教精神の普遍化と国家神道批判;柳田国男における民間「神道」観の成立とキリスト教―「国民倫理」形成と神社合祀政策批判;柳田国男における「固有信仰」と「世界民俗学」―キリスト教との関連から)
第2部 現実の政治認識と学説(一九二〇年代の柳田と吉野の政治思想―「共同団結の自治」と「政治的自由」;「デモクラシー」と「生存権」―吉野作造と福田徳三との思想的交錯;「共同団結の自治」実現への模索―「民俗」の価値および神道政策への提言;吉野作造の「現代」政治史研究―政治史講義を中心に;「郷土研究」とアカデミズム史学―「神話」研究の再興及び歴史資料編)
「大正デモクラシー」の学問の特徴
「新しい歴史学」と「我々の文化史学」
著者等紹介
田澤晴子[タザワハルコ]
1966年東京都生まれ。名古屋大学大学院環境学研究科博士後期課程修了。岐阜大学教育学部准教授(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ブックウォーカーの提供する「読書メーター」によるものです。
てれまこし