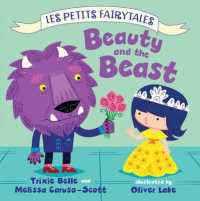内容説明
過酷な労働環境から抜け出すために海賊となり、権力に抵抗した近世大西洋世界の船乗りたち。本書は、不遇の立場に置かれた労働者や奴隷の声に耳を傾け、四大陸の相互連関を考究する「アトランティック・ヒストリー」の観点から、海賊たちの姿を鮮明に描き出す。虐げられてきた人々がいかに団結して苦境に立ち向かっていったのか。彼らの真実の物語を明らかにする歴史家レディカー渾身の書、待望の邦訳。
目次
第1章 二つの恐怖の物語
第2章 海賊行為の政治算術
第3章 海賊となる者
第4章 船上の新たなる統治
第5章 「水夫に公平な扱いを」
第6章 女海賊ボニーとリード
第7章 「奴らを世界から一掃せよ」
第8章 「死をものともせず」
終章 血と黄金
著者等紹介
レディカー,マーカス[レディカー,マーカス] [Rediker,Marcus]
歴史家・市民運動家。ペンシルヴェニア大学で博士号を取得し、現在、ピッツバーグ大学歴史学科の大西洋史(アトランティック・ヒストリー)特別教授。抑圧された環境に置かれた労働者階級こそが歴史を作り上げてきたとの信念に基づき、社会史研究において「下からの歴史」を実践。近世大西洋世界の船乗り・海賊・奴隷を扱った数々の著作で知られる。市民運動家として、人権や平和のための運動にも積極的に参加している(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
1 ~ 1件/全1件
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
サアベドラ
13
海賊の社会史。著者はピッツバーグ大学特別教授で、近世の大西洋における水夫や奴隷などの下層民を専門とし、近年盛んな「環大西洋史(アトランティック・ヒストリー)」の旗手。スペイン継承戦争終結後の約10年間、いわゆる「海賊の黄金時代」に暴れまわった海賊達の社会的・文化的・経済的背景を紐解きながら、彼らがなぜ海賊になり、どのような思想を持ち、どのように死んでいったかを描き出す。著者は海賊を犯罪者としてよりも虐げられた下層民として捉えようとするところがあるので、その点は多少差し引いて読んだほうがいいかもしれない。2016/07/24
左手爆弾
4
海賊研究の第一人者による海賊史。海賊とは貧しき様々な国の群集であり、自らを民主的に組織し、一般の人のために生きるまっとうな男達と自己規定していた。さらに、当時の労働待遇が劣悪だった商船に比べ、海賊船には社会福祉制度まであり、女性の自由も一足早く実現していた。こうした歴史的事実があるからこそ、人々は海賊に魅せられ続けるのだろう。なお、これだけの海賊史研究の大家が「海賊は基本的に即物的だったから×印のついた宝の地図を残すことは考えられない」と断言しているにもかかわらず、ハンターは後を絶たないらしい。南無。2015/06/29
陽香
3
201408102016/06/15
oldman獺祭魚翁
2
図書館本 内容的にはカリブ海賊の最後期フランス系バッカニア(ロロノア・モンバール等)からイギリス系の海賊に移った以降の話がメインです。内容・エピソード共に興味深いのですが、随所にみられるマルクス史観にはいささか閉口しました。確かに後期海賊は私掠船からよりも、反乱や船の掠奪からの物が多いですが、当時の船乗りをそこまで「虐げられた人民」扱いするのもどうかと思います。後期の海賊は確かに一見民主的でしたが、逆に強烈なカリスマ性を持ったリーダーが居なかったこと自体が、その存在を短命に終わらせたのではないでしょうか?2014/12/17
Seiji
1
レディカーさんの海賊に従事する人々は支配階級に対する抵抗であると指摘する点が特徴的です。社会学からするとそういう意識を持つ人たちもいたことでしょうが、みんながみんな抵抗意識を持っていたとは言えません。海賊と支配者側に分けて捉えるなら、レディカーさんは海賊側からの視点が強いです。
-

- 電子書籍
- 主人公のママになります【タテヨミ】第5…
-
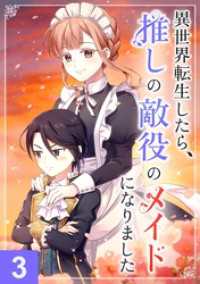
- 電子書籍
- 異世界転生したら、推しの敵役のメイドに…