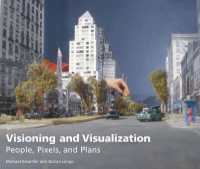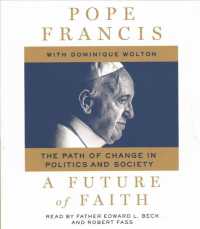内容説明
現在、日本にはラブホテルと呼ばれる施設があるが、カップルが利用する貸間には、連れ込み宿やモーテルなど様々な名称が付けられ、消えていった。姿・形は変わっても同じシステムや機能を持った空間が、なぜ時代によって変化してきたのか。本書では、日本の貸間空間の変遷をもとに、外観や経営者の変化を取り上げ、その名称が人々の性意識を色濃く反映させてきたことを解明する。『ラブホテル進化論』の著者が描く、待望の通史。
目次
序章 ラブホテルのルーツ(出合茶屋、船宿、待合;ラブホテルに近い「円宿」の出現)
第1章 連れ込み旅館の成り立ち(「連れ込み旅館」に至るまで;普通の旅館から連れ込みへ;「連れ込み」の目印)
第2章 モーテル(ホテル)の誕生と衰退(アメリカのモーテル;日本のモーテル;類似モーテル)
第3章 ラブホテルの隆盛(デラックス化されたラブホテル;女性が喜ぶファッションホテル)
第4章 ラブホの現在(「ラブホ特集」の影響;ラブホの現在)
著者等紹介
金益見[キムイッキョン]
1979年大阪府生まれ。在日コリアン3世。神戸学院大学大学院人間文化学研究科地域文化論専攻博士後期課程修了。現在、神戸学院大学非常勤講師、大手前大学非常勤講師(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
1 ~ 1件/全1件
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
ケー
19
前著『ラブホテル進化論』と大まかな流れ、主張は同じ。連れ込み宿から始まり、モーテルの時代を経てラブホテルの出現、その変遷を論じる。だが、今回は出版形態がハードカバー、かつ前回は紙幅の都合で細かくは言及できなかったであろうラブホテル経営者や広告業者、編集者へのインタビューが豊富に収録されており、より充実した内容。考察に関して用いられている態度はかなり民俗学的アプローチが強め。写真資料が多く、巻末のラブホテル年表も非常に密度が濃く、面白かった。2018/10/30
ふろんた2.0
7
連れ込み宿からラブホテルまでの変遷を追った文化史。温泉マークの由来は初めて知った。2016/02/09
ともたか
7
研究論文かなぁ。地方の新聞をも隅々まで読んで書いたものらしい。 如何なるものにでも向かっていく気持ちが大切なのだろう。2016/01/31
きいち
7
街道筋のモーテルも街中のお城も子供の時はかなり謎だったもの。広告やインタビューを地道に使って、連れ込み宿が今のラブホになるまでを実直にたどる。劇的なストーリーではなく、いろんな商売人さんが環境の変化とやむにやまれぬ事情にさまざま対応して出来上がってきたんだなあ、ということが伝わってくる。それにしても、論文そのままな感じ、ミネルヴァらしいな。2013/01/03
かす実
4
ラブホテル(性行為をするために部屋を貸す施設)の歴史的変遷についての研究論文という感じ。資料もたくさん参照されていて、よく調査されているなあと思った。ド派手なお城のような古いラブホテルが多いのはなぜだろうと思っていたが、派手な外観それ自体が広告として機能していたこと、建てれば儲かる時代があったこと、多くは個人経営だったこと、などがその理由として紹介されていて納得した。ラブホテルだけでなく旅館全般の女性経営者の多さとか、温泉マークが性風俗を意味する時代があったとか、興味深い知識を沢山得た。2021/08/08
-

- 電子書籍
- 【電子版限定特典付き】凶乱令嬢ニア・リ…