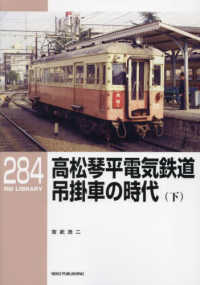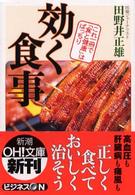内容説明
子どもの遊びは変わったのか。子どもたちのおかれている複雑に入り組んだ現代社会を読み解き、子どもにとっての遊びの意味に迫る。
目次
1 遊びの見方(「かくれんぼ」ができない子どもたち―子どもの居場所;「この指とまれ」ができない子どもたち―遊びの創造;「ブランコ」がこげない子どもたち―身体遊びの復権)
2 遊びの仕方(遊び環境としての大人たち―社会的親になるために;遊びに変える能力をはぐくむ―子どもらしさの再生)
著者等紹介
杉本厚夫[スギモトアツオ]
1952年大阪市生まれ。1978年筑波大学大学院修士課程修了。1978年広島大学総合科学部助手。1986年京都教育大学教育学部助教授。1996年京都教育大学教育学部教授。2010年関西大学人間健康学部教授(現職)(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
hiace9000
33
社会学の視点で教育・子どもを観ると「普通はそういうもの」の"普通"に対しても課題が炙りだせるようだ。社会との結節点、つまり一番痛みや歪みが出やすい子どもの世界は、大人のありようを意図せずとも如実に映してしまう鑑。子どもの育ちの現場に身をおくと、本書が指摘する課題を事実として痛感。今年から変わった指導要領で小学校では「主体的に学びに向かう態度」が評価の観点に。子ども達に主体性を育むための、主体的思考・行動をいかにして学べる場を創出するかー、そのための「遊び方」=「生き方」を独自の視点から示した一書。2020/11/28
とろこ
10
鬼になったとき心細いからかくれんぼができなかったり、ブランコの漕ぎ方がわからなかったり、食堂で「お醤油取って」がどうしても言えない、などにわかには信じがたい事例も多い。「最近の子どもは…」というが問題は大人の側にある、と言い切っているのが斬新。状況を憂うだけでなく、親子キャンプなどを企画して改善に動いているところも良い。ただ、アツいのを通り越して「?」な部分も少なからずあったので、友人同士で「これはやばいよねー」と話をする域を出ないというのが正直なところ。もう少し冷静な根拠があれば。2013/05/09
バニラ
5
「遊びごころ」の教科書。すごく良い本だと思う。2019/09/16
たこやき
4
子供の遊びから現代の社会を、というのだが、肝心の、前提となる社会事象、子供の状況についての根拠が示されないので納得できなかった。「~が増えている」「~と実感している」が正しい保証ない。そこに社会学の理論を当てはめても……。また、ゲームなどについて、著者の無知などもあり短絡的な議論が目立つ。後半の著者が行っている活動については興味深いが、その解釈も含めて疑問は多かった。2011/12/26
こどもおねむ
2
前半は子供たちの遊びについて、かくれんぼやブランコなどを例にあげながら、数十年前と現代の子供たちの遊びに対する考え方や遊び方の違いと、その違いの意味とそれによる問題点の提起、簡単な対処法など。 後半は著者が長年行ってきた、子供と親の触れ合い講座や、遊びのキャンプについて、プログラムの流れ、趣旨、そしてその時の様子について。 前半はデータも多いが、著者の主張が強い所もあり、評価は分かれる。常時オンラインの環境で考えるとまた違うかもしれない。 キャンプなどは部分的に極論は否めないが、経験としては良い試み。2020/11/10