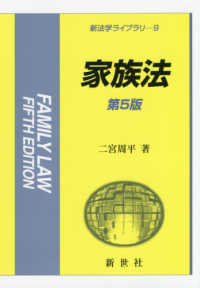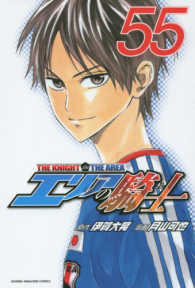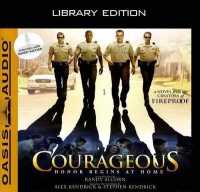出版社内容情報
【内容】
人口と家族を社会を構成する基層として設定。人口と家族がどのように社会の構造を規定し、またその変動が社会の変動とどのように関連していたかを探る。「人口篇」では、「人口史」から「歴史人口学」への展開を試みる。
【目次】
はじめに
序 歴史人口学――課題・方法・史料(速水 融)
1 徳川時代におけるクライシス期の死亡構造(木下太志)
2 18世紀初頭の奥会津地方における嬰児殺し
――嬰児の父親が著した日記を史料として(川口 洋)
3 宗門改帳と懐妊書上帳
――19世紀北関東農村の乳児死亡(鬼頭 宏)
4 明治期の乳胎児死亡
――北多摩農村の一事例(斎藤 修)
5 近世刈谷町における人口移動規制(松浦 昭)
6 毎月指出控帳の分析
――和泉国塔原村の出生と死亡(三浦 忍)
7 近世後期漁村における人口増加と出生力の分析
――肥前国彼杵郡野母村の事例(津谷典子)
8 徳川農村における「出生力」とその近接要因
――「間引き」説の批判と近世から近代の農村母性をめぐる考察
(友部謙一)
事項索引/人名索引/地名索引
内容説明
本書は、人口と家族を、社会を構成する基層として設定し、近代以前のユーラシア社会において人口と家族がどのように社会の構造を規定し、またその変動が社会の変動とどのように関連していたのかを探る。人口篇では、「人口史」から「歴史人口学」への展開を試みる。
目次
序章 歴史人口学―課題・方法・史料
第1章 徳川時代におけるクライシス期の死亡構造
第2章 十八世紀初頭の奥会津地方における嬰児殺し―嬰児の父親が著した日記を史料として
第3章 宗門改帳と懐妊書上帳―十九世紀北関東農村の乳児死亡
第4章 明治期の乳胎児死亡―北多摩農村の一事例
第5章 近世刈谷町における人口移動規制
第6章 毎月指出控帳の分析―和泉国塔原村の出生と死亡
第7章 近世後期漁村における人口増加と出生力の分析―肥前国彼杵郡野母村の事例
第8章 徳川幕府における「出生力」とその近接要因―「間引き」説の批判と近世から近代の農村母性をめぐる考察
著者等紹介
速水融[ハヤミアキラ]
1929年東京に生まれる。1950年慶応義塾大学経済学部卒業。慶応義塾大学教授、国際日本文化研究センター教授を経て現在、麗沢大学国際経済学部教授。専門研究分野は近世日本経済史、歴史人口学
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
-

- 和書
- かなの美