出版社内容情報
第一次世界大戦はいつ終わったのか? 1918年11月だ。だが、戦争の敗者にとって、それはまさに暴力の始まりだった。
ハプスブルク帝国、オスマン帝国、ドイツ帝国、ロシア帝国の崩壊、革命と反革命、再編された国家間の紛争、それに重なる内戦。400万を超える人々が武力紛争で死亡し、中欧・東欧・南欧の難民が荒野をさまよい歩いた。「戦後」ヨーロッパは、地球上で最も暴力的な場所になった。
第一次世界大戦とは専制主義に対する民主主義の勝利であり、崩壊した帝国は時代錯誤な「民族の牢獄」であったという従来の見方は、この事態を見過ごしてきた。だが、1917年から1923年のヨーロッパは、第二次世界大戦、そして20世紀を席捲した暴力を理解する上で決定的な意味を持つ。
確かな実証性と明快な論理で無数の紛争を一冊に纏め上げ、新たな歴史像を見せてくれる本書は、第二次世界大戦におけるナショナリストとファシストの台頭を解き明かし、第一次世界大戦の本当の意味を問い直すものとして、世界的評価を得た。
内容説明
未曾有の紛争が大量虐殺の論理を生んだ。敗北者にとって、戦後はまさに暴力の始まりだった。帝国の崩壊、内戦、ファシズムの台頭。20世紀を決定付けた暴力の起源を照らし、現代史の新たな扉を開く。
目次
プロローグ
第1部 敗北(春の列車旅行;ロシア革命;ブレスト=リトフスク;勝利の味;運勢の反転)
第2部 革命と反革命(戦争は終わらない;ロシアの内戦;民主主義の見せかけの勝利;急進化;ボリシェヴィズムの恐怖とファシズムの勃興)
第3部 帝国の崩壊(パンドラの箱―パリと帝国問題;中東欧の再編;敗れたる者に災いあれ;フィウーメ;スミルナからローザンヌへ)
エピローグ―「戦後」と二〇世紀半ばのヨーロッパの危機
著者等紹介
ゲルヴァルト,ローベルト[ゲルヴァルト,ローベルト] [Gerwarth,Robert]
1976年ベルリン生まれ。現在、ユニバーシティ・カレッジ・ダブリン現代史教授および同大学戦争研究センター所長。専攻は近現代ヨーロッパ史。とくにドイツ史
小原淳[オバラジュン]
1975年生まれ。早稲田大学大学院文学研究科博士後期課程修了。現在、早稲田大学文学学術院教授。専攻はドイツ近現代史(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
Toska
健
たばかるB
MUNEKAZ
ケイトKATE
-
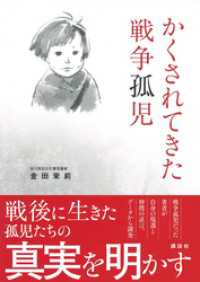
- 電子書籍
- かくされてきた戦争孤児
-
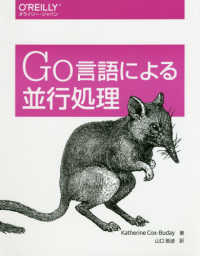
- 和書
- Go言語による並行処理






