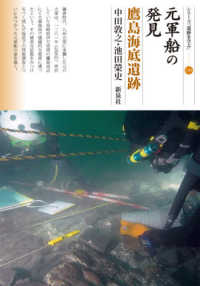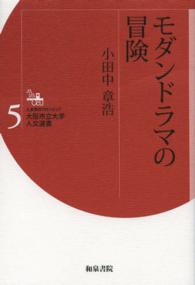出版社内容情報
はるか宇宙の果てをさぐるにせよ、微細な素粒子を扱うにせよ、物理世界の理解を目ざして探求を始めるとき、私たちは必ず「数学」という言語を自明の基礎として用いる。しかし、数学へのこのような信頼には根拠があるのだろうか。数学とはいったい何であり、なぜうまく働くのだろうか。
『万物理論』の著者バローによるこの問いかけから、読者は数学の起源、意味、謎をめぐる魅惑的な旅に引き込まれることになる。古代の計数文化からコンピュータへ、ピュタゴラスからヒルベルト、ゲーデルへ。立場を異にする数学者たちの悲喜劇を交え、練達の道案内が展開されていく。
数学とは数学者によって「発見」されるような真理なのか、それとも実際上の必要に迫られて人間が発明した人工物にすぎないのか。数学とは一種の宗教なのか。プラトン主義に拠るならば「π」はまさに天空にある。苦闘の歴史を刻んできた20世紀数学。現在、次なる可能性を見守る地点にわれわれは立っている。
John D. Barrow(ジョン・D・バロー)
1952年、ロンドンに生まれる。ダーラム大学卒業後、1977年、オクスフォード大学でPh.D.(天体物理学)を取得。オクスフォード大学、カリフォルニア大学バークレー校を経て、1981年にサセックス大学に移り、1999年まで天文学教授および同大学天文学センター長を務めた。現在 ケンブリッジ大学教授。著書『宇宙はいかに創られたか』、『万物理論』『宇宙が始まるとき』ほか多数。
林 大(はやし・まさる)
1967年、千葉県生まれ。東京大学経済学部卒業。翻訳家。訳書 ザイエンス『光と視覚の科学』、バーリンスキ『史上最大の発明アルゴリズム』ほか。
-----------------------------------------------------------------
関連書:
J・D・バロー『万物理論――究極の説明を求めて』
R・ペンローズ『心の影 1――意識をめぐる未知の科学を探る』
R・ペンローズ『心の影 2――意識をめぐる未知の科学を探る』
R・ペンローズ『皇帝の新しい心――コンピュータ・心・物理法則』
I・プリゴジン『確実性の終焉』
内容説明
数学とは何だろうか。どういう意味を持つのか。古代の計数文化から、カントルやゲーデルまで、『万物理論』の著者による案内に耳を傾けながら数学哲学の世界をめぐる、華麗なるオデッセイ。
目次
1 神秘から歴史へ
2 カウンター・カルチャー
3 形あれども中身なし
4 発明主義の母
5 直観主義―けがれなき構成
6 頭上と内のプラトン的天空
著者等紹介
バロー,ジョン・D.[バロー,ジョンD.][Barrow,John D.]
1952年、ロンドンに生まれる。ダーラム大学卒業(1974年)後、1997年、オクスフォード大学でPh.D.(天体物理学)を取得。オクスフォード大学、カリフォルニア大学バークレー校を経て、1981年にサセックス大学に移り、1999年まで天文学教授および同大学天文学センター長を務めた。現在、ケンブリッジ大学教授。重力理論の宇宙論的側面を専門とするが、260篇に上る論文に加えて、天文学、物理学、数学をテーマに一般読者のために書かれた多数の著書があり、英語圏でもっとも多産なサイエンス・ライターの一人としても知られている
林大[ハヤシマサル]
1967年、千葉県生まれ。東京大学経済学部卒業。翻訳家
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
やいっち
七波