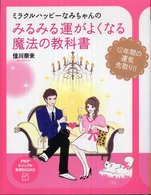感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ブックウォーカーの提供する「読書メーター」によるものです。
いとう・しんご
7
リクールきっかけ。オルフェウス教について知りたくて読みましたが、ホメロス(R.ベネディクトに言及しつつ「恥の文化」と評価)から前ソクラテス期、プラトン(オルフェウスはここに登場)を経てアリストテレス、ヘレニズム時代までのギリシャの信仰の変遷を教えてくれます。文化人類学の知見や両大戦前後の社会不安の経験などを反映させながらの歴史解釈はとても生き生きとして、頻出するギリシャ語の鬱陶しさを忘れさせてくれます。アレキサンダーの時代以降の宗派乱立の背景に「自由の恐怖」を読み取る歴史観は共感できました。2023/04/17
ヴィクトリー
5
再読。何かと理性的・合理的な面ばかりが取上げられがちな古代ギリシアの非理性的な面を扱った本。イリアスの英雄たちに自由意志的なものが乏しいように見えたり、夢の話などが扱われているが、面白かったのが魂の考え方にユーラシアのシャマニズムの影響が見られる、と言う説。脱魂、長い睡眠の伝説、転生、魂と肉体をはっきり分けて考えるようになった事などがそうらしい。スキタイ、トラキアから伝わったとすれば、それほど荒唐無稽でも無いのかも。古い本(1951)なので、今はどういう扱いなのかは知らないけど。2014/09/10
ヴィクトリー
2
注の数、量ともに多く(本文の2/3ぐらい?)読み進めるのにすごく時間がかかってしまった。特に第1章の注には「イリアス」「オデュッセイア」の該当箇所を記すのみで内容が分からないものが多く、それらの本を開いて確かめていたので異様に時間がかかった。注に飛ぶ度に本文を中断して読むので全体的な理解が結構あやしい。再読が必要か。それでも戯作や歴史書、哲学書など多様な文献の残る古代ギリシアは当時の人々の心性を知るのにはよい時代ではないか、と思い興味が湧いてきたことは収穫か。2012/08/20
differenciantum
1
益子陶器市へ向かう電車のなかで読了。大学生の頃に読んで以来の再読。初読のときはずいぶん興奮して読んだ記憶がある。いまにして思えばいささか極端な主張だとも思えるがそれはそれとして、文献学だけに拠らず、かといってハイデガーにも頼らず、人類学や比較宗教学、深層心理学を活用した学際的な古代ギリシア哲学の読解の可能性を切り開いた点では、功績が大きい本。第7章のプラトン読解はたいへんユニークで、この路線を継いだ本はいまだに読んだことがない気がする。2018/04/30
Norihiko Shr
0
再読。なれど著者の主張がサッパリ掴めてこない。おれはバカなのか?再々読決定だな。ちっ。2013/12/07