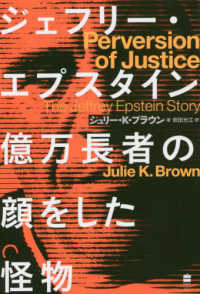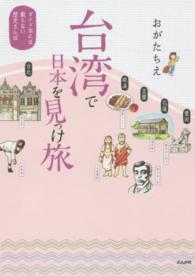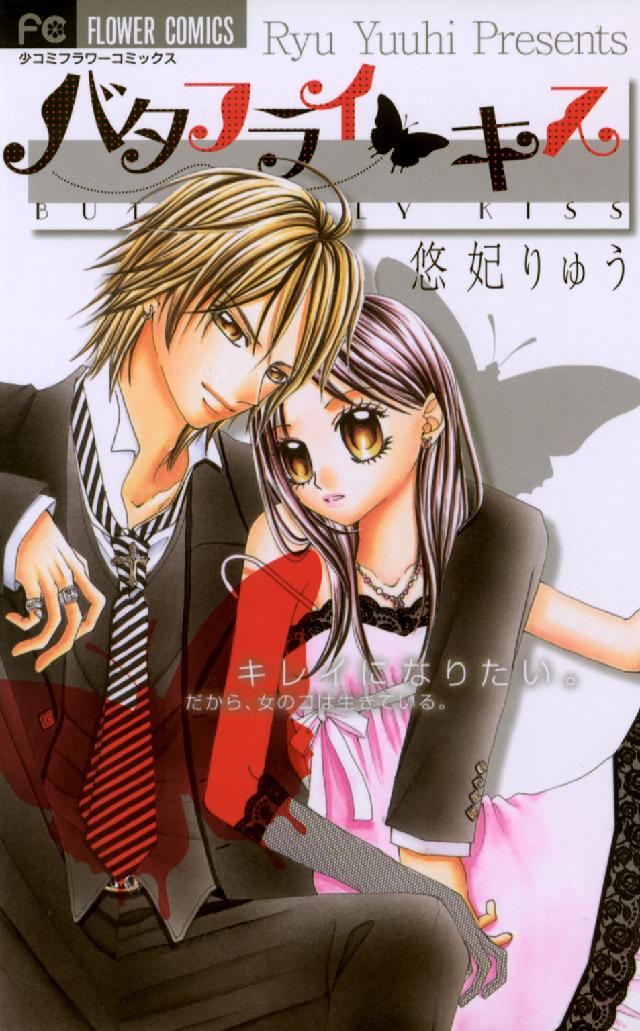内容説明
谷川俊太郎、俵万智、田村隆一、吉増剛造、宇多田ヒカル…。深く豊かな表現によって時代に光芒を放つ詩人たちを解読し、「感性の現代史」を描き出す。練達の批評が語る詩の真髄。
目次
現代詩とは何か
谷川俊太郎
田村隆一
塚本邦雄
岡井隆
俳句という表現
夏石番矢
吉増剛造
歌詞という表現
中島みゆきと松任谷由実〔ほか〕
著者等紹介
吉本隆明[ヨシモトタカアキ]
1924年東京生まれ。詩人、評論家。東京工業大学卒。文学のみならず、社会、宗教など広範な対象への批評活動は、戦後思想史上にオリジナルな達成を築いた
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ブックウォーカーの提供する「読書メーター」によるものです。
かふ
20
戦後の「荒地」派から短歌・俳句、流行歌まで詩歌全般について形式論をわかりやすい言葉で伝えている。それは吉本本人の批評ではなくて聞き書きだからかエッセイのように読める。詩の形式が日常を表現するようになって簡易化された。一方で神話などの物語性を求めていく難解詩もあり、その両極端に内輪になっているのか?この本を詠む前に岡井隆のインタビュー集を読んでいたら吉本隆明との討論で完璧に叩かれたとあった。そして『言語にとって美とはなにか』で吉本に叩かれた歌人で有名になったとか。岡井隆も重要歌人として褒めていた。2024/10/03
ヴェネツィア
14
ひさしぶりの吉本隆明。なんだか別人みたいだ。毎日新聞に連載されていたようだから、読者向けに平易に語ったのか(おそらくは、書いたのではなくて、隆明が語ったのを編集者が文字にしたものと思われる)、あるいは御歳78歳(連載当時)という年齢が彼をかくも丸くしたのか。ここでは、塚本邦雄や寺山修司から、果ては中島みゆきや宇多田ヒカルまで語られている。美空ひばりだって登場する。インテリゲンチアが、ガムラン音楽の異国情緒は受け入れるのに、日本の情緒を受け入れないのはおかしいと言うのだけれど。2012/06/22
マッピー
11
洋の東西を問わず、詩というのは小説より断然芸術性が高いということになっている。そして私は、絶望的に詩の読み方がわからない。何しろ一つの言葉に込められた意味の層が熱すぎる。告白。読み終わっても気づかなかったのですが、この本既読でした。詩が苦手な割に、詩についての本を読みたがる。そして全く記憶に残らない…。私の感性どないやねん!2019/05/23
chisarunn
6
表題通り萩原朔太郎を初めとする現代詩を、「表現としての特徴を元に」中島みゆき、宇多田ヒカルに至るまで注釈してある。半分くらいは知らない詩人だ。特に象徴主義の詩は、「読んだけどわけわからんかった」というくくりで覚えているという情けなさだ。その中で、吉増剛造という詩人の場合。「言葉がその詩人の内面の表現になっているのが象徴主義の詩だが、言葉と内面が切り離されていながら、価値のレベルでは結びついている」と解釈されている。そうそう、こういうふうに言ってもらえばわかるんだよ。読んでみよう。2021/06/12
マッピー
4
詩が苦手なんです。 解説文を読まないと、良さがわからない。 言葉に対する感性が鈍いのかな、と思うことしばしば。 わかりやすいストーリーがないと、腑に落ちない。 そんな私は、短歌でも俳句でも現代詩でも、解説文を読むのが好き。 わからなかった言葉の並びが、突然意味のあるものになるから。 この本は、吉本隆明のところへ編集者2人が訪ねて行って、詩について、詩人について語ったものをエッセンスにしてまとめたもの。 詩は言葉であり、リズムであり、メロディーであるのかもしれない。 2017/06/30