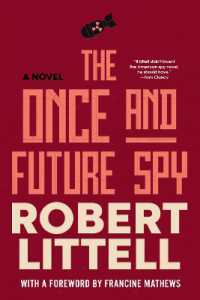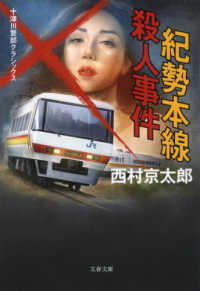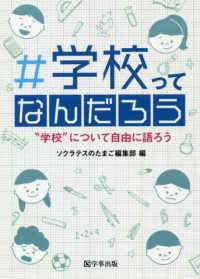内容説明
小学校の理科の教科書で、必ずしょうかいされるプランクトン。しかし、どんな生きものなのか、教科書ではくわしくふれていません。この本では、みずうみやいけ、ぬまなどにいる植物プランクトンのすがたにせまります。植物プランクトンは水の中にいますが、地上の植物と同じように、光合成をして生きています。また、動物プランクトンのエサとなることによって、多くの生きものの命をささえています。さまざまな植物プランクトンの、ふしぎなくらしをけんび鏡でのぞいてみましょう。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
☆よいこ
81
公共図書館の電書で読了。植物プランクトンの特徴は「光合成」ができること▽[ボルボックス]300個~6000個の細胞で球体をつくる[ミカヅキモ]粘液をだして動く[クチビルケイソウ]殻に覆われている[カスミマルケイソウ]円盤型[サヤツナギ]細胞がこがね色[イカダモ]敵がいるところではたくさんくっついて大きくなる[アオミドロ]30cmくらい長くつながることもある[クンショウモ]4の倍数[ネンジュモ]役割の違う細胞がつながる[ミクロキスティス]アメーバ状▽面白い。2018年発行の本を底本に2021年電書発行2025/07/08
遠い日
11
大きな大きな写真で、小さな小さな植物プランクトンを学ぶ。サヤツナギ、ミクロキスティスというプランクトンは知らなかったなぁ。光合成の力は、本当に不思議ですてき。2018/06/07
マツユキ
9
植物プランクトンって、何だっけ?大きな写真で見るプランクトン。習ったはずなんだけど…。新鮮!2019/07/05
7a
7
私は何と言ってもボルボックス。繁殖の仕組みがとても面白いので好き。娘はクチビルケイソウが気に入ったそうです。これは動物プランクトン版も読まねば。2018/05/19
ワタナベ読書愛
1
2018年発行。小中学校の理科の資料集あたりで見たことのあるボルボックス、ミカヅキモ、アオミドロなどの植物プランクトンが大きく引き伸ばされた写真と、大型本ならではの大画面で楽しめる科学絵本。写真では見づらいからだの構造はイラストで解説。上から見るとでかいが、横から見ると貧相なものもあって意外性が楽しめる。植物プランクトン業界の有名どころのプロフィールがわかる。これを知っていると、その辺の池や沼、田んぼ、水場、家の水槽などに「あんなやつがひそかに住んでいる」と思えて楽しい。星や月など宇宙っぽいフォルムも素敵2021/05/23
-
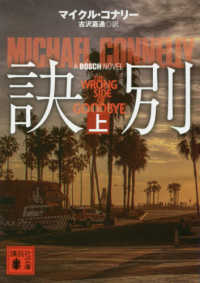
- 和書
- 訣別 〈上〉 講談社文庫