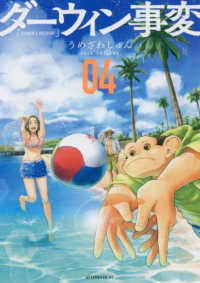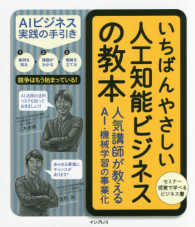内容説明
「草紙の文化は江戸の花である。路地の日常に咲く他愛ない花である。…浮世絵や草双紙などの無駄花のことを、またその無駄花を、無駄を承知で温存していた時代、社会のことを知りたかった」(「おわりに」より)―直球勝負は難しい「ふつう」の文化を知ることのために、著書は、浮世絵や草双紙が生活のなかに入ってゆく窓口たる「絵草紙屋」に焦点をすえる。遊里や芝居の情報をはじめ絵と言葉で流行の先端を告げ知らせ、絵本やおもちゃを売って子どもと大人のお楽しみを演出し、土産物を提供して江戸らしさのセンターとなり…、「ふつう」の文化の前線基地の実相を、膨大に収集した資料を駆使して探り描きだす。近世文化の生きた姿をとらえる著書ならではの一冊。
目次
第1章 絵草子屋の風景
第2章 江戸の絵草紙屋
第3章 地方の絵草紙屋と草紙類の広域的流通
第4章 上方の絵草紙屋
第5章 子どもと草紙、子どもと絵草紙屋
第6章 絵草紙屋消滅
著者等紹介
鈴木俊幸[スズキトシユキ]
1956年、北海道生まれ。中央大学大学院博士課程満期退学。現在、中央大学文学部教授。専攻、書籍文化史(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
isao_key
6
著者は「乱暴に言ってしまえば、江戸と言う年の出版文化を代表するものは、浮世絵を中心とする草紙類であろう。江戸の草紙類は、江戸という年の象徴であり隠喩でもある」と述べている。本書はその草紙類を販売していた絵草紙屋についてたんねんに調べ上げた力作である。浮世絵の中には例えば、他国への草紙類の出荷が大げさに描かれている。当時の江戸以外への出荷はそれほどあったとは思えないが、あえて大げさに描くことが地本問屋の繁栄となり、江戸っ子の誇りでもあったという。江戸発信の文化がこの浮世絵という草紙によってはじめて実現した。2014/08/08
果てなき冒険たまこ
4
「草紙の文化は江戸の花である。路地の日常に咲く他愛のない花である。花は腹の足しになるものではない。生活に直接役に立つものではない」んだけど、江戸期から明治前半にかけてみんな大好き♡で門前市を成すように絵草紙屋には人が詰め掛けていたという今じゃ考えられない文化的光景。まぁ実際には文化というより今のSNS的な感じでライトに楽しんでたんだろうけどね。最終章の絵草紙屋消滅は儚いねぇ、清方先生の記憶を通してしかもう実感できないんだろうなぁ。2025/06/26
なおこっか
4
新鮮な時事ネタを扱い、それ故に消耗品的な扱いの絵草紙。江戸生産の草紙は地本と言われ、そもその土地で出来その土地で消費される物。蔦重の店は問屋の趣き。浮世絵の小売が発展すると、店先のディスプレイも賑々しくなってくる。草紙が江戸土産にもなる。絵草紙屋は印刷屋、出版社、雑貨屋、様々な成り立ち。浮世絵を購入すると、絵草紙屋が店名、住所、取り扱い商品、支払条件等を印刷した掛紙でくるっと巻いて渡してくれる、その掛紙から店の様子を辿るというのが初見で面白かった。明治20年頃から衰退してしまうが、花袋や鏡花の文には残る。2025/01/16
メルセ・ひすい
2
14-67赤66今、再び世界は日本かわゆい江戸とれんど文化。ジャポニズムの第二次沸騰期 ! 21世紀はこれも軸として売りまくれ ! コンナンデマシタ !? 世界最高の真似のできない精密機器と江戸文化をさらに熟成・醸成して世界の文化を凌駕し洗脳セヨ…。文化ミサイル戦略攻撃。人工衛星も多用し世界各国の主要都市へ文化親善ミサイルを炸裂セヨ 神道・仏教パワーだっ!…( ^0^)2011/03/09
しまちゃん
0
江戸時代の情報発信の装置であり、大人から子供までが絵草紙に夢中になっていたことが、この本から知ることができます。 「情報産業の最右翼であった」絵草紙を扱う地本業界が、絵葉書(写真)の出現により衰退していったというこの本の最終部分には時代の移り変わりを感じます。2011/06/18