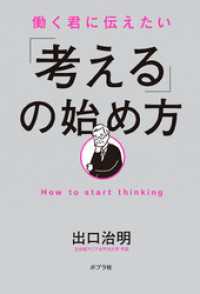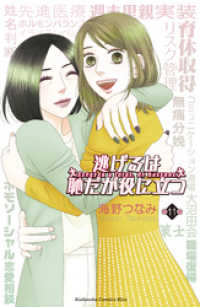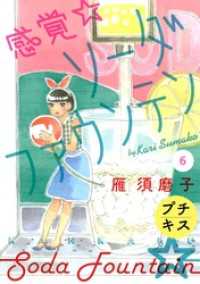出版社内容情報
男たちは「家造り」を小説に書き続け、女たちは「家出」ばかりを書いてきた。明治から150年の小説群を「家」で読み解いたときに見えてきた、日本の家、家族、家庭の形。
内容説明
明治から令和までに書かれた大量の小説群を、「一冊の大河小説」として読む、破天荒な試み。小説には、家制度の解体から核家族化を経て、一人暮らしが激増する現在までの「家」や「家族」、そして、その時の「私たち」が、何を感じ、望み、考えてきたのかが、繰り返し描かれてきた。戦争やパンデミックで孤立や分断が進むいま、小説は「私たち」の、どんな苦悩と希望を映すのか。世界文学へと続く、十二作品の論考を増補。
目次
第1章 借家の文学史
第2章 生きられた家・描かれた家(家族の家の時代;部屋の時代;離合集散の時代)
第3章 持ち家と部屋の文学史(ドールズ・ハウスの舞台 建築の様式と小説の様式―継承と変化;小島信夫「うるわしき日々」―最後の「父の家」小説;津島佑子「風よ、空駆ける風よ」―「母の家」小説の変化;漂流する部屋―「居場所」探しの冒険物語)
第4章 文学は、大河から海へ向かう(黒川創「かもめの日」;岸政彦「図書室」、「リリアン」;白尾悠「サード・キッチン」 ほか)
著者等紹介
西川祐子[ニシカワユウコ]
1937年東京生まれ、京都育ち。京都大学大学院博士課程修了。パリ大学大学博士。日本とフランスの近・現代文学研究、女性史、ジェンダー論専攻(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
Inzaghico (Etsuko Oshita)
Peter-John
Fumoh
こさと
よっちん