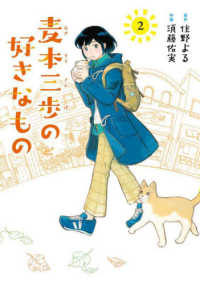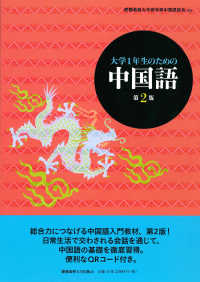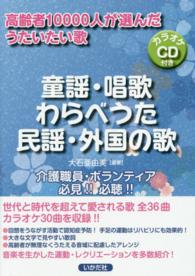内容説明
ルネサンスとは何であるか、が絶えず問われている。過ぎさった歴史ではなく、現代につながるものとして、現代人にとっての新しいルネサンス像がここにある。哲学・科学・教育・美術・文学・印刷術・図書館など、一三章にわたって論じられたさまざまな考察は、著者ガレンの卓抜な見識・学殖と相俟って、読者に大きな知的刺激を与えるだろう。
目次
ルネサンスと文化
新しい時代という意識
古典の発見
ギリシア人とルネサンスの起源
人文主義とルネサンス―連続か対立か
図書館と印刷術の発明
新しい教育
政治的省察に関する主題と問題―現実の都市と理想の都市
批判と宗教的刷新の動機
新しい哲学―人間と自然の賞揚
新しい科学―人間と世界の認識
人文主義文化と国民文学
美術―建築、彫刻、絵画
著者等紹介
ガレン,エウジェニオ[ガレン,エウジェニオ][Garin,Eugenio]
1909‐2004。中部イタリアのリエーティ生まれ。ルネサンス研究の碩学、元スクオーラ・ノルマーレ・スペリオーレ(ピサ)名誉教授
澤井繁男[サワイシゲオ]
1954年、札幌生まれ。作家・関西大学文学部教授。東京外国語大学卒業、京都大学大学院修了。博士(学術)。イタリア・ルネサンス文化専攻(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
Olive
6
しつこく何度も読んでわかってきた。文献学の復活と歴史意識の革新から”常に”誕生している中世の学者たちの汗と結晶である古典古代発見の成果である。難解な文章に多数の研究者の名前に閉口したが、中世とルネサンス、人文主義とルネサンスは連続か対立かではなく、古典を師とし新たな法則に則った自由学芸の研究は、古代の権威からの開放であった。人文主義のルネサンス期による学芸の研究は、宗教勿論政治、哲学にも波及する。そこには新しい教育があり、ローマを追われアヴィニョンへ渡った教皇とローマとの対立→2021/03/11
うえ
4
「一年前キケロの未知の演説数篇をすでに発見していたポッジョは、サンクトガレン修道院に向かい…修道院長ハインリヒ三世の許しを得て、一群の著名な文献を発見し、コンスタンツに持ち運んで写させ、友人全員と古典作品を愛読する人たちに連絡をとった…ポッジョやその友人と追随者は、古代の知の正当な特徴を見つけ出さねばならぬと痛感している。そして初めは粗雑でも徐々にいっそう洗練された技術で原典を文献学的に再構成して、ひとつの文明全体を遡り、歴史的次元の意識を獲得しかつ批判能力を磨きながら…現在の知と対置させるようになる。」2024/11/16
ちあき
4
イタリアの文化史家による概説書。新書では物足りない読者向けのよい本だとは思う。教育システムについて記述した7章、カスティリオーネ『宮廷人』とマキァアベリ『君主論』を対比させながら政治の言語を論じた8章は非常におもしろい。しかし、著者の博識さが発揮されるほど固有名詞の洪水におぼれそうになる文化史概説書の宿命は逃れられなかった印象。文芸作品はテクストの引用がもう少しあった方が初学者にとって親切な本になったと思うのだが。ドレスデンの『ルネサンス精神史』もよい本なので平凡社ライブラリーで復刊お願いします担当の方。2011/04/22
Fumoh
3
非常に難解な書ですが、実際に言っていることは各研究書で言われている事実の確認ばかりで、真新しい内容は何一つないと思います。帯に「この一冊でルネサンスが分かる」とありますが、とんでもありません。余計わかりにくくさせる説明だと思います。というのは、詩的で難解ではっきりしない表現が多く、それはひとえに衒学趣味のためだと思われます。たとえばp,80「一方地球は、中心にあろうが周縁にあろうが、動的であろうが不動であろうが、神に対して相対的で無限な領域に存在するのである。世界と神との比較について何と言おうと、それは2025/04/14
kyohei
3
ユマニスム、ギリシャ信仰への回帰、反トマス(スコラ)のような一言に片付けないルネサンス史。教育の章はかなり読み応えがありました。科学についても面白い。文化史といっても広範囲で論じられるので、簡単にでも思想史や科学史のような、論じられる分野の知識があると幾分か楽に読めるかと。2012/07/04
-
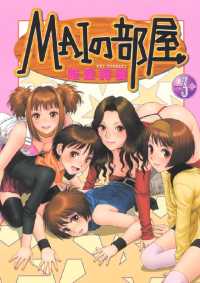
- 電子書籍
- MAIの部屋(3)