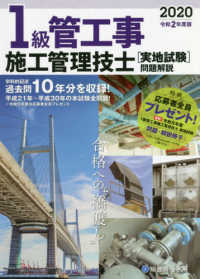出版社内容情報
生活骨董は、実際に使い、そして育むもの。
生活骨董は、実際に使い、そして育むもの。例えばひとつのお盆をお皿にもお膳にも見立てて工夫して使う。著者の体験を通じて綴った珠玉のエッセイ集。
骨董というと、一般的には高くて、知識が必要で、高尚なイメージがあり、興味はあるが買うには腰が引けてしまうという人が多いのではないでしょうか。しかし、著者の麻生圭子氏がこの本で提案する「生活骨董」は、けっして敷居の高いものではありません。その名のとおり鑑賞や蒐集を目的としない生活のための骨董であり、些細で質素な道具たちを実生活に取り入れ、使いこなしていくものです。ガラクタ呼ばわりされている古道具でも職人の手によるものであれば、その職人の心が感じられ、使い心地が違うものです。
▼著者の麻生氏は東京から京都に移り住み、町家で生活をしています。つまり、生活の場自体が骨董なのです。本書は、その日常生活の体験から紡ぎ出されたものであり、京都での骨董に囲まれた生活、生活骨董から見えてくる心の置きどころ、骨董屋さんとのつきあい方がテーマとなっています。また、骨董のカラー写真もふんだんに入れています。
●第1章 私と骨董
●第2章 生活骨董から見えてくる、心の置きどころ
●第3章 京都の骨董屋さん
●第4章 本物を使うことの意味
内容説明
生活骨董は、ただ単にながめるだけのものではなく、実際に使い、育むものです。たとえばひとつのお盆をお皿にもお膳にも見立て、工夫して使う。そこに新しい発見があり、生活骨董との美しい関係が生まれるのです。著者の体験を通じて綴ったエッセイ集。
目次
第1章 私と骨董(古民家暮らし;骨董の根っこ ほか)
第2章 生活骨董から見えてくる、心の置きどころ(蒐集はしない;骨董は捨てなくていい ほか)
第3章 京都の骨董屋さん(京都の骨董屋さん;てっさい堂 ほか)
第4章 本物を使うことの意味―うるわし屋 堀内さんとの対談(嫌いなものを売って、ほしいものを買う;昔の漆器の魅力は、表情の豊かさに、価格 ほか)
著者等紹介
麻生圭子[アソウケイコ]
80年代に作詞家として小泉今日子、吉川晃司などのヒット曲を手掛ける。96年から、京都に移り住み、99年には築70年の町家での暮らしを始めた
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
-

- 電子書籍
- コンプ厨、ファンタジー化した現代を行く…
-

- 和書
- 別れの時