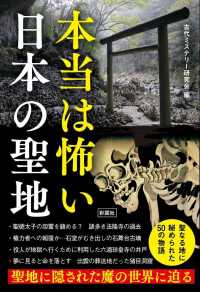出版社内容情報
近代ベトナム美術はどのようにして出現したのか。本国と植民地、前近代と近代、東洋と西洋の文化が交錯する1887年から1945年までのフランス統治下のベトナムの美術・藝術を分析、その発展を解明。第1回東京大学而立賞受賞作。
内容説明
1887年から1945年までのフランス領インドシナ政府統治下で出現したベトナム美術の発展の歴史を解明する。第1回東京大学而立賞受賞作。
目次
第1部 美術と技術 一八八七~一九二三年(フランスから見たベトナム藝術―「安南藝術」とは何か?;三度の博覧会―「美術」との邂逅と工藝の領有;植民地における技術教育―手仕事の軽視を乗り越える ほか)
第2部 二つの「ルネサンス」 一九二四~一九三一年(植民者たちの「ルネサンス」と装飾の復興;ファム・クインと岡倉覚三の「ルネサンス」;ベトナム知識人たちの「安南ルネサンス」 ほか)
第3部 フランスとベトナム 一九三二~一九四五年(ナム・ソンの『中国画』;ファン・チャンとベトナム絹画の誕生;絹の上のアオザイ美人像―レ・フォー、マイ・トゥ、ヴ・カオ・ダン ほか)
著者等紹介
二村淳子[ニムラジュンコ]
白百合女子大学文学部准教授。国際日本文化研究センター客員准教授。比較文化論、藝術・美学、文化研究専攻。東京大学大学院総合文化研究科博士課程中退。博士(学術)。ライターとしても活躍(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
内島菫
19
個人的に多様性という言葉は都合良く使われすぎて逆に胡散臭く感じられてもいたのだが、本書は多様性というものが本当に使われるべき場所は歴史なのではないかと気づかせてくれる。時間を超えて残ったものは残っていないものから成っている、ということこそが、矛盾や軋轢、消滅さえも含んだ本来的な意味での多様性なのではないだろうか。また歴史の糸は一本ではなく、複数の糸が撚り集まり絡まりながら、マイ・トゥの絵のように多声的で一番大きな声さえ聞く人によって異なる。本書は、ほとんど聞こえないような小さな声にも耳を傾け、2021/10/18
-

- 電子書籍
- 365誕生星占い~1月14日生まれのあ…