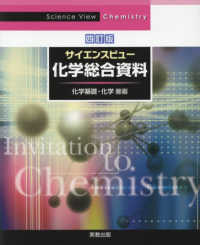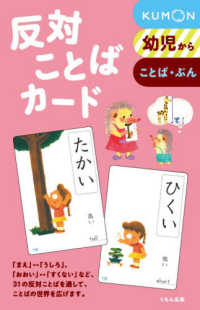出版社内容情報
内容説明
アッパー・クラスの人々はイギリス国内でどういうイメージをもたれてきたか。その印象・誤解・実像を、文学と著名な人々の例を通して、背景事情とともに読み解いていく。
目次
第1章 貴族の称号
第2章 「ヤンガー・サン」とアッパー・ミドル・クラス
第3章 カントリー・ハウスと相続
第4章 アメリカン・マネー
第5章 ステイトリー・ホーム観光
第6章 アッパー・クラスの教育
第7章 アッパー・クラスとオックスフォード大学
第8章 新しいアッパー・クラスと「ブライト・ヤング・ピープル」
第9章 現代のアッパー・クラスのイメージ
著者等紹介
新井潤美[アライメグミ]
東京大学大学院比較文学比較文化専攻博士号取得(学術博士)。東京大学大学院人文社会系研究科教授(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
1 ~ 1件/全1件
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
パトラッシュ
124
なぜ英国ミステリには遺産相続絡みの殺人が多いのか。上流階級と庶民の格差と古い慣習が、繰り返し文学や映画の主題になるのはなぜか。ほとんど政体の変更を経験せず長子相続制が長く維持された島国で、他に見られない独特の価値観と国民性が形成されていった結果だったとは。誇り高い一方で金持ちのアメリカ人女性と結婚したり、高額の税金を払うためカントリーハウスを公開するなど現実的な世故に長けている矛盾が面白い。同じ島国ながら明治維新と敗戦ですべてがシャッフルされた日本と比べ、固守すべきものを持つ国と国民の強さが見えたようだ。2022/03/14
南北
59
イギリスの貴族や爵位はなくても由緒正しい家柄の人々についてついて書かれている。まずは貴族に対する手紙の宛名や社交の場での呼びかけ方に圧倒される。爵位は基本的に長男が受け継いでいくので、長男と次男以下の呼び方が異なっていたり、夫人への宛名から離婚していることや元夫の貴族が再婚していることまでわかってしまったりする。そんな上流階級だが、地主としての収入が減ってしまったため、館を観光客に公開することで維持したりして、いろいろ苦労が絶えないようだ。興味深い点も多く、文学作品を読む上でも参考になると思った。2022/02/02
サアベドラ
33
ドラマ『ダウントン・アビー』やジェイン・オースティン、イーヴリン・ウォーの小説などに登場する19世紀~20世紀の英国の上流階級(アッパークラス~アッパー・ミドルクラス)について、称号や結婚と相続、所領の維持、教育などのトピックを文学作品などをソースに解説した本。2022年刊。著者の専門はイギリス文学における社会階級の表象で、本書以外にもイギリスの様々な社会階級に関する著作が多数ある。『ダウントン・アビー』以外ほとんど知らないレベルで手に取ったが、まったく知らない世界を垣間見ることができて十分楽しめた。2022/07/22
KF
23
二冊続けて新井潤美さんの書を読んだが、子供の頃から接していたはずの英語の、その背後にある英国文化については全く知らない事ばかりだな、と痛感した。大学を卒業し英文学士(英語学士だったかな?)を取得しているものの英語の技量には多少興味を持っていたが文学についてはほぼ素通りだった事を思い知らされた。日本人が目にする英米文学は米国製のテレビ番組や映画が主であり、英国文化に於ける「階級」とその影響については読んでいてもなかなか理解し難い印象だった。共感しようと思えば文学や文化に多少馴染まなければ難読の域を出ない。2025/08/11
ごへいもち
23
やっと読了。面白く読みました。久しぶりにちゃんとした本を読んだかも2022/08/23
-
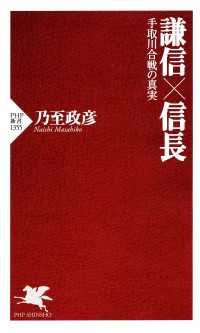
- 電子書籍
- 謙信×信長 - 手取川合戦の真実