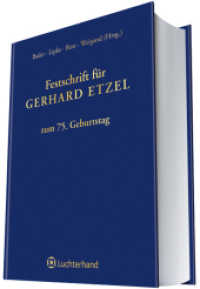内容説明
考えるな、見よ!ここまで親しみやすく語られた彼の哲学があったろうか。かけがえのない日常の「場」でこそ、言語ゲームは繰り広げられる。「カジュアルの極北」を目指す新たなウィトゲンシュタインが、レヴィナスやソシュールとスリリングに遭遇し、「語りえないもの」へと限りなく接近していく。
目次
第1部 「ことば」(個体発生(ウィトゲンシュタイン哲学)は系統発生(西洋哲学)を繰りかえす
「哲学」って、いったい…?
「語の意味」って、突然言われてもなぁ… ほか)
第2部 「倫理」(「倫理」というのは難しい、本当に;レヴィナスの倫理は、すごいと思う;数学で言えば、「顔」というのは公理のことです ほか)
第3部 「たしかなこと」(「確実なこと」は、確実じゃない;「非対称」という私たちののがれようのないあり方;「示す」と「語る」という区別は、とても大切 ほか)
著者等紹介
中村昇[ナカムラノボル]
1958年、長崎県佐世保市生まれ。中央大学文学部教授(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
ころこ
31
前期と後期の間に中期を設けて「文法」とするのは永井均と同じです。言語の使用に抵触しないというのが前期と後期の明らかな違いですが、それが前期と中期の断絶になっており、理想から現実へという哲学史になぞらえているのは慧眼です。本書の特徴は、あることを語るためにその周りのことを熱心に語っているというまさに言語的な語りにあります。ベルクソン、ソシュール、レヴィナスなどが取り上げられ、むしろそれらの理解の助けになりますが、思考とはその様なものでしょう。そのどれでもないという形でウィトゲンシュタインが浮かび上がります。2020/11/19
うえ
7
現象学への言及「フッサールであれば、自分自身の意識が、なんといっても最も確実なのだから、そこから自分もふくめた世界全体をもう一回説明しなおそうじゃないか、ということ…そうするとこの「超越論的主観性」のなかに、他人も世界も、なんでもかんでも入っている…なんで他人が入ることができるのだろうと、フッサールは、晩年までさんざん悩むことになります。「他我構成」と言われるやつです。自分自身の我から出発して、他人の我が同じように存在していることを説明しようとする。何かとてつもなく無理しているような印象をいつも受けます」2025/07/27
T2C_
5
恐ろしく砕けた文体でウィトゲンシュタインの思想を噛み砕いて解説した一冊。この書籍で言及されたのがウィトゲンシュタインの思想の内どれ程の範囲かはわからないが、「考えるな、見よ」のスタンスが非常に共感出来たというか。普遍性や絶対性が存在しない事が証明されたと言えそうな現代思想上で、ゾンビに成らなくて済みそうな印象を受けた。言語ゲーム(に関連するソシュールに端を発する言語の捉え方)や非対称性、差異の記述は非常に興味深く、その斬新さから考える軸が増やせた。上手い事消化して言葉を丁寧に紡げる様になれたら嬉しい。2015/12/07
脳疣沼
4
これまで読んできたウィトゲンシュタイン本の中で一番優しく分かりやすい。なんで他の解説者はこうやって書いてくれなかったのだろう?と思うほど。ただし書きっぷりが気に入らない人もいると思う。2018/05/25
Go Extreme
2
論理空間と命題の対応 独我論の主張 錯綜する言語ゲーム 生活形式という独特なかたち 疑えない言語ゲームの基盤 否定による意味の成立 固定点なき循環 適切な発話でゲーム進行 何も隠されていない事実 考えず見ること 重なり合う類似性の網 家族的類似が言語ゲーム 言葉は特別なことではない 徹底した現場主義 言葉は複数による理解 混合状態のイメージュ 違いと類似の相互補完 世界に不在の絶対的価値 からだの魂 知るー知らない以前の領域 私的言語の不可能性 脱色された語の本質 方法的懐疑の限界 非対称な世界の認識2025/05/10
-
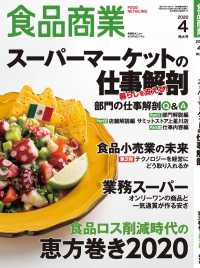
- 電子書籍
- 食品商業 2020年4月特大号 - 食…