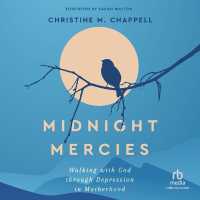出版社内容情報
「にぎやかな過疎」とは「過疎地域にもかかわらず、にぎやか」という、一見矛盾した印象をもつ農山漁村のこと。14章からなる本文に加え、「農的関係人口」などの基礎用語を、著者独自の視点で解説するコラム「農村再生キーワード」を11記事収録。註には本書の背景の深掘り解説や、参考図書の紹介なども多数盛り込む。農村再生のための政策構想を論じた『農村政策の変貌』(2021年)の続編であり、コロナ後の社会と2025年基本計画以降の展開を見据え、農村の過去~現在、そして未来への展望まで総合的に見通す一冊。
内容説明
この国に住む私たちは未来世代にどのような国土を引き渡すことができるのか?豊かな「人口減少社会」を描く農村再生論、待望の書!
目次
第1部 農村再生の方向―持続的低密度居住地域(持続的低密度居住地域をつくる―本書の課題;「農村たたみ論」批判)
第2部 農村問題の理論と政策(農村問題の展開―課題地域問題から価値地域問題へ;地域づくりの新展開)
第3部 農政と農村政策(新しい農村政策の意義―2020年基本計画を読み解く;食料・農業・農村基本法の在り方―見直しの論点 ほか)
第4部 国土の広がりと地域政策―過疎法・地方創生(過疎法の展開(1)―2010年改正法の位置づけ
過疎法の展開(2)―2021年過疎法を展望する ほか)
第5部 にぎやかな過疎をつくる―新たな政策課題(「にぎやかな過疎」の現在地;新たな政策課題―持続的低密度居住地域の展望)
著者等紹介
小田切徳美[オダギリトクミ]
明治大学農学部教授。専門は農政学・農村政策論、地域ガバナンス論。東京大学大学院単位取得退学、博士(農学)。(財)農政調査委員会専門調査員、東京大学農学部助手、高崎経済大学経済学部助教授、東京大学農学部助教授等を経て、2006年より現職(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
けんとまん1007
うえぽん
1.3manen
N_K
-
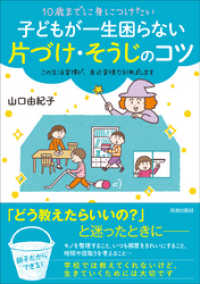
- 電子書籍
- 10歳までに身につけたい 子どもが一生…