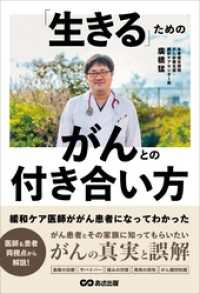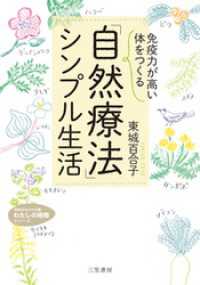内容説明
近代国家やそのもとでの「民主主義・自由・平等」の限界があらわに。ゆきづまる近代的世界を超え、どのような未来社会を構想するか。山村と都市を行き来しながら労働や共同体をめぐる独自の思想を形成してきた哲学者が、平明な言葉で語る。
目次
序文 神話としての近代世界
第1講 国家が意味を失う時代に(民主主義は成立しうるのか;たそがれる国家;民主主義と民主王朝制;近代世界の建前について;近代理念の崩壊;分解と混乱を極める世界)
第2講 未来への構想力と伝統回帰(現在のさまざまな伝統回帰;上野村の伝統回帰について;農村の伝統回帰とは何か;未来社会のデザインは農業、農村にある;討論から―ポジション取りとシステム保守を超えて)
第3講 関係的世界への回帰(「死者は存在するか」という問いに対して;実体本質論の限界;伝統思想がみた関係的世界;関係を成立させる「場」について)
第4講 どこに根を張るか(世界市場か、結び合う市場か;根の張った経済社会へ)
著者等紹介
内山節[ウチヤマタカシ]
哲学者。1950年東京生まれ。東京と群馬県上野村を往復しながら暮らす。立教大学大学院21世紀社会デザイン研究科教授などを歴任。NPO法人・森づくりフォーラム代表理事(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
tamami
43
以前から、著者の内山節先生の考えに触れる度に、自分の足下にありながら、普段顧みることの少ない本来の自分の姿を思い浮かべ、その破れの指摘に心から納得して、明日に備えようという気持ちになるのだった。本書でも、例えば西洋の社会の構成員は生きている人間だけなのに対し、日本の場合は、まず自然と人間が作る社会であり、人間については死者を含めるという。また、本質的なものは実態ではなく関係なのだと言われる。そして関係作りの始めに挨拶があるという。仏壇に手を合わせ、家族に挨拶するところから始まる。社会のあり方指南の書。2021/04/10
pirokichi
17
職場のトップが「健全な民主主義社会の実現…」とあまりにもよく口にするので、『民主主義を問いなおす』というタイトルに惹かれ手に取った。知人が著者のファンなので私も著書を讀みたかった、というのもある。特に第3講「関係的世界への回帰」が胸に響いた。「神は確かに存在する」のでなく「関係を結んでいるから神様はいる」には納得。また「「私」もまたいろいろな関係の総和」では先月読んだ平野啓一郎さんの「分人」を思った。本書は「東北農家の二月セミナー」での著者の報告を3部作としてシリーズ化したもの。続く2、3も読んでみたい。2021/04/15
みーあ
0
★3.5 内田樹氏と思って図書館で借りたら、内山節氏だったという…but.内山節氏のエッセーも地元紙で読んでいて惹かれる哲学者の一人だったのでうれしく読み進めた。内田樹氏が言う「コモンの再生」と、内山節氏が言う「関係づくりは場づくり」というのが、同じことを言っているように聞こえた。で、その方向性が良いように感じる。2026/01/03
オニオオハシ
0
関係の話が面白く、自分の中で「神の存在の有無」について最大限に納得できる答えを得ることができた。2025/12/14
半崎クジラ
0
ものごとを問うときは、言葉を大切にしていかないといけない。「民主主義」についても、僕が理想として漠然と描いている姿と、それがいかなる理想のもとに掲げられてきたか、については隔たりがある。物事を「足元」から考え直さなきゃいけない時代が来ているという感覚があって、それは「根」「コミュニティ」と言った言葉からなんとなくみんなの中で共有され始めているのかな、と思う。国家というシステムの現在。関係ありき、というのもそうだが、現実問題として実体というものに立ち向かうなら、それは実体の側から解体すべきなのかも、とも。2024/04/24