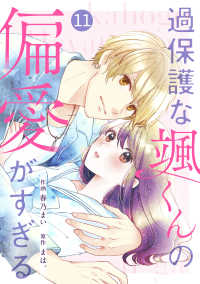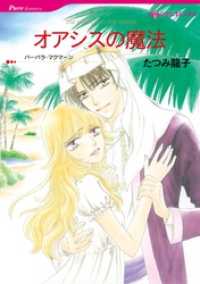内容説明
権力を見て経済を忘れず、経済を見ては権力の動態を知ろうとする。通貨問題とは、そうした視点の往復運動によってはじめてとらえることのできる何ものかだ。ニクソンショックから円圏構想、ユーロの本質、人民元論議まで、現代史と覇権分析の視点で問う異色の通貨論。
目次
第1章 ニクソンショックの深層
第2章 人民元をあえて経済から見ない
第3章 通貨と通貨が戦うとき
第4章 ブレトン・ウッズ体制とは何だったか
第5章 ユーロの宿命
第6章 潰えた円圏の夢
第7章 ドルの将来をどう読むか
著者等紹介
谷口智彦[タニグチトモヒコ]
日経BP社編集委員室主任編集委員。1957年香川県生まれ。81年東京大学法学部卒業後雑誌『現代コリア』、株式会社東京精密を経て85年12月~2003年8月『日経ビジネス』記者、主任編集委員。この間米プリンストン大学フルブライト客座研究員、ロンドン特派員、ロンドン外国プレス協会会長、上海国際問題研究所客員研究員を歴任、現在米ブルッキングズ研究所北東アジア政策研究センター・フェロー、ワシントン滞在中
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
田山河雄
1
本書は2005年3月の出版、ニクソン政権の頃だ。だから10年前のアメリカに身を置いて書いた書物ということになる。非常に興味深い…がなんと難しいのだろう、理解が出来ないのだ。ニクソンショックから、ブレトンウッズ体制とは何だったのか…とか、ユーロの宿命など、当時の米国の置かれた状況を前提にその危機意識の上に米国の政治経済的苦慮を…、或は憎っくき日本経済への対処攻撃論等をも論じている。同調する必要はないが、その謂わんとする事を理解しないことには対応のしようがない。我が国経済学者にその様な反論論文があっただろうか2015/05/17
lostwatch
1
通貨は政治。然り。政治的な強固な意志無しに強い通貨は作られず。面白い。こういう本はあまりない。2011/02/23
ゐたふ
0
ブレトン・ウッズ体制について知るため、主に第一・四章を読んだ。本書が採る立場は非常に興味深い。すなわち、ニクソン・ショックは完全に想定可能だったという立場である。これは、同体制が抱える制度的欠陥を論拠とした説である。さらに面白いのは、これに反論する松井均氏の説についても紹介されている点で、トリフィンのジレンマという問題を考察する上では実に参考になる。それでも、本書は上記の立場をとる。「ドルのみに金との交換性を与えたところから、全ての問題は発生した。」この一文は強烈であり、是を以て、私は筆者に賛同したい。2014/11/19