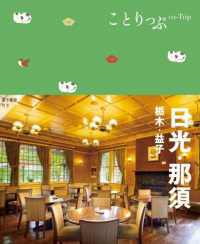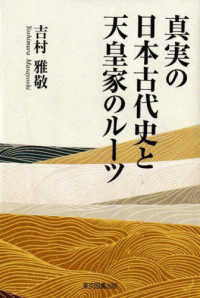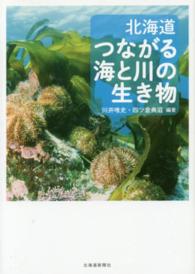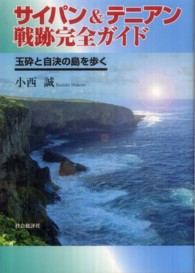内容説明
激変するビジネス環境、会社はどこへ向かうのか。会社員は何をすべきなのか。
目次
特集 会社がわかる(日本企業の「知」を考える(野中郁次郎)
会社員の幸福論―中間管理職こそ「部下力」を身につけよ(佐々木常夫)
オリンパス、大王製紙、九州電力…会社が道を誤るとき―タテマエとホンネの会社の仕組み(森一夫))
サラリーマンの一生 会社人間になってみる(楠木新)
3・11後の不動産を読む!安心と安全を重視しながら、資産保有のリスクは敏感に(幸田昌則)
あなたの隣の経済学 なぜ編集者の机はたいてい散らかっているのか(佐々木一寿)
「上から目線」の真相 なぜ過剰に「上から目線」になってしまうのか(榎本博明)
ここは進化の袋小路 会社に寄生する元部長氏は、適応進化した細菌と同じ(植木不等式)
孫子をいま読む理由 短期決戦で勝てないなら、「不敗」を目指してみる(守屋淳)
ワイン・コンシェルジュ 昇進・新築・結婚祝い…相手の好みを知らずとも、ハズさないワインの選び方とは?(柴田さなえ)
小説 社長のテスト(山崎将志)
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ブックウォーカーの提供する「読書メーター」によるものです。
s.asada
2
サブタイトルが「激変するビジネス環境、会社はどこへ向かうのか会社員は何をすべきなのか」。この巻も11人の著者がおり、佐々木常夫氏の「会社員の幸福論」、「オリンパス、大正製紙、九州電力の不祥事」(森一夫氏)の部分が読みたいパートでした。「人事部は見ている」で有名になられた楠木新氏が書いている「一人前になるのに10年かかる」という説は他でもよく聞くが、神戸大学大学院の教授が海外の研究を含め「10年ルール」を研究されていることは知らなかった。それにしても日経はタイトルが上手い。これだけで会社がわかる訳がない。2012/01/01
Sato1219
1
日経文庫や日経プレミア新書などの執筆者が少しずつ寄稿した、オムニバス・アルバムのような本。もちろん、オムニバスで満足できなくなったら、(あるいはもっと深堀りしたくなったら)、そのひとの著作まで手を伸ばせばいいわけで、このようなつくりの本の意義というのはやっぱりあると思う。面白いことは、「会社がわかる」というテーマで本を編んだとき、今やかなりの比重を、ヒトの問題で占めていると言うこと。とはいえ、この問題、他の経営分野と比べても、誰もが一家言持つも、ついに確たる答が見いだせていないのだ、と改めて思う。2012/04/17
Daisaku Arita
1
会社のことはわかりませんでした!!でも、おもしろい。管理職の最も重要な役割についてや、今のミドルが弱くなっている理由等、鋭い指摘だなと思います。佐々木常夫氏の章は人間味が溢れていてとても共感できました。2012/02/07
るーさん
1
会社がわかるって書いてあったけど、そんなにわかりませんよ苦笑ためにはなるかなあっていうのが部下力!あとは10年で一人前になるってところですかね。上から目線について言及しているところがおもしろい考察だなって思いました。2012/02/03
yashiti76
0
2⃣よい習慣は才能を超える!仕事のできるできないは、能力の差ではなく習慣の差!オリンパスや大王製紙のドキュメントは面白かった。ただ、タイトルと中身がズレてる気が。。。2013/08/15