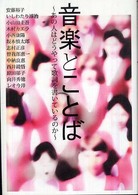内容説明
“塩”と“砂糖”は、私たちの生活になくてはならないモノです。それは身体にとっての必要成分であり、和覚においても重要な位置を占めます。さらに、昔から食品を長期保存できるようにするモノとして使われてきました。
目次
第1章 砂糖の本当の姿とは?(砂糖はなぜ白いのか?―それは何度も不純物を取り除いた純度の高い証し;砂糖の原料は?―主に甘しょからとる「甘しょ糖」とてん菜からとる「てん菜糖」 ほか)
第2章 砂糖の力―食品をどうやって保存する?(砂糖は水を抱え込み微生物の増殖を抑えて保存性を高める―自由水を少なくする;砂糖には「賞味期限」というものがない―変色したり固まっても一切問題ナシ ほか)
第3章 塩とはいったいどんなもの?(塩は「塩化ナトリウム」、サイコロ形の結晶で、白く見えるのは光の乱反射;塩は工業用としても多様に用いられている―医薬や火薬、石鹸、金属精錬など ほか)
第4章 塩の力―食品をどうやって保存する?(梅干しには塩分で種類がある―22.1%を「梅干」、7.6%を「調味梅干」という;温泉で洗う「野沢菜漬け」、建礼門院が名付けたともされる「柴漬け」 ほか)
第5章 塩と砂糖と人間の体(砂糖の1グラム当たりのカロリーは蕎麦やパンと同じ―しかしとり過ぎは問題;体全体の20%のエネルギーを消費する脳のエネルギー源は唯一「ブドウ糖」 ほか)
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
ひー坊
13
読みやすい文章でサクッと読める。入門用として調度イイ。しかし脱字が目について、きちんと校正されてないんだなあとちょっと気になった。2025/03/20
Junya Akiba
1
ご近所の方と「クレイジーソルトは万能で大活躍!」という話で盛り上がったが、実は岩塩は苦味があって肉に合い、海の塩はちょっと甘くて、、、と、奥が深そうなので図書館で通りすがりに目についた本書を借りてみた。砂糖と塩の歴史、分類、製法、応用いろいろ分かって楽しい。小学生の頃、塩田(の跡地?)のそばに住んでおり、学校で「流下式塩田」の製法を習ったのを覚えているが、1972年には既に廃止になっていた製法を学んでいたのか、、、。おもしろサイエンスシリーズを初めて読んだが、いろんな意味でとても楽しい。2019/07/07
T
0
P148 「塩=高血圧」という見方にも注意を促します。というのは、塩分のとり過ぎによって高血圧になる人は、高血圧患者の約1〜2%に過ぎず、高血圧患者の約9割は原因の特定できない「本態性高血圧」とされているからです。 P150 人間の体の中で塩分調節機能を果たしているのが腎臓です。これは、きわめてすぐれた機能で、「1日35グラムの範囲で塩分をとっても血圧に支障なく正常な生活が送れる」という発表がされています。2022/10/21
-

- 洋書
- One Love