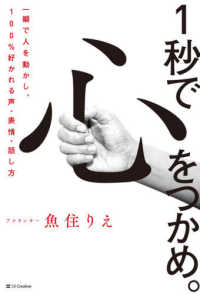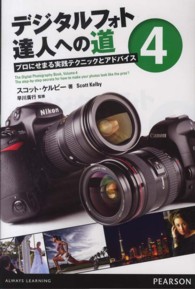目次
1 電力政策の行方(どうなる原子力発電;見直し必至の再生可能エネルギー;時代先取りの電力自由化を)
2 次世代エネルギー事業者(エネルギー市場の将来を占う;次世代を担うエネルギー事業者)
著者等紹介
井熊均[イクマヒトシ]
株式会社日本総合研究所執行役員。創発戦略センター所長。1958年東京都生まれ。1981年早稲田大学理工学部機械工学科卒業、1983年同大学院理工学研究科を修了。1983年三菱重工業株式会社入社。1990年株式会社日本総合研究所入社。1995年株式会社アイエスブイ・ジャパン取締役。2003年株式会社イーキュービック取締役。2003年早稲田大学大学院公共経営研究科非常勤講師。2006年株式会社日本総合研究所執行役員(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
Takeshi Tokushige
1
もはや情報古し。
ミッキーの父ちゃん
1
1985年の通信の自由化以降、電電公社はNTTになり、通信業界の状況は大きく様変わりしました。 1995年に一旦は自由化された電力の自由化は頓挫した形になっていますが、2016年を目処に小売の完全自由化を目指すようです。 その結果何が起こるかは読んでもよくわかりませんが、現在の「電力会社」「ガス会社」「石油会社」の業際がなくなって、サービスも多様化するんだろうということは想像できました。 KDDが携帯電話サービスを手がけたり、インターネットのプロバイダーになるなんて思いもしませんでしたから…2014/03/21
ごはんりれー
0
この分野を知りたい時に一番最初に読んだほうが良いかもしれない本(要点しかないので、読みやすい)。色々調べた後に読むと、内容が薄くまだwikiのほうが内容が濃い。。だけど新たな知見として、今までは知らないことがあればまずwikiとかで調べてたけど、改めてwikiを見ると内容が整理がされていて良かった。なので最初だけwikiを見るのではなく、何十冊かその分野の本を読んだ上で改めてwikiを見てみると、知識が整理されるという利点があった。2015/01/07
HARU
0
改革により東電は送配電部門をコア事業としていくと。発電事業には新規参入が相次ぎ、50/60ヘルツの違いから実際競争が起こるのは東電管内を中心とした東日本。現在は原発停止中のため電力需要も逼迫しているが2020年時点ではかなりの数が最稼働し電力は供給過剰に陥ると。そもそも、日本の原発はアメリカが冷戦時に極東アジアに核技術を配備するために建てたものであり、日米同盟有る限り全面停止はあり得ない(故に民主党はスポイルされた)とのこと。今後コスト競争力ないと淘汰される。石油火力、老朽設備との入れ換えがまず起こる。2014/03/29
Yasunari Hatada
0
電力システム改革に関する国民的な期待の高まりを受けて2020年の電力市場の状況を予想した1冊。表紙にあるように、「原発復帰」「FIT(再生エネルギー固定買取制度)」「電力自由化」「東電改革」について議論されている。おそらく筆者が本書の中で一番期待しているのは「東電改革」であって東電の会社の抜本的な改革を実施することが、従来までの電力市場の形式を大きく変化させ、4月に閣議決定された「電力システム改革案」を大きく後押しすることになると論じている。電力関連の仕事をしている人は読んでおいて損はない本だと感じた。2013/06/08