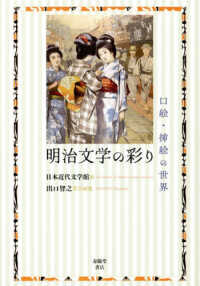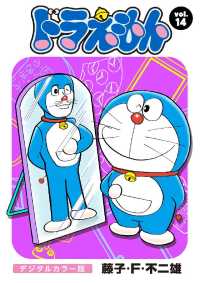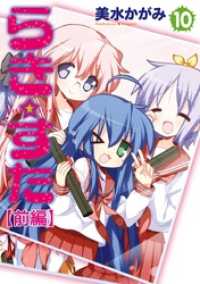出版社内容情報
《内容》 ICUで遭遇する可能性のある様々なトラブルをいかに防ぎ,またいかに対処するかという視点から書かれた独創的なマニュアル.点滴ラインがとれない,妊婦が痙攣で入室してきた,突然の停電など,患者管理をすすめるなかで生じる多彩な問題に対する解決策が懇切に解説されており,状況に応じた対処をするための実践的な応用力を養うことができる.単なる個別の処置の羅列にはとどまらず,通読すればICUで最良の診療を行うために必要な知識と考え方が身につく. 序 アメリカで研究生活を過ごした後,帰国して気づいたこと,あるいは新しい発見といえるものがいくつかある.その一つがアメリカのマニュアル本の優秀さである.これは絶えず人が(外国人も含め)流動的に動き回り,しかも言語能力に乏しい人,風俗習慣に疎い人でも社会を構成する一員としてそれなりの活動をしてきた,この国の歴史の流れの中で生まれ,かつ成熟してきたものであろう. このため著者のように知識が乏しく不器用な人間でも,マニュアルを見ていれば,あの国では始めて扱うパソコンもさほど苦もなくこなし,自動車のちょっとした故障などは自力で直すことができたのである.日本では従来「技術は盗んで覚えろ」というように,教えぬことがよい教育であるかのような風潮があった.しかし教育病院のような,発展途上の人間を多数擁して仕事をしているところでは,そう悠長なことは言ってはおれない.熱意や根性は決して結果を保証してくれるものではないし,累々たる患者の犠牲の上に獲得された技術や知識など,決して褒められたものではない.マニュアル本の値打ちとは,一人前でない人でも,とりあえず人並み程度に仕事ができるようにするところである. 本書のタイトルである「トラブルシューティング」というのは,向こうのマニュアルでよく見掛ける言葉であり,文字通り,困った時にそこを読めば解決の道が開けるというストレートな問題解決を目指したシステムである.本書で選んだ121の項目は,著者の日常臨床の中で,どうしたらいいか悩むこと,研修医が間違えやすいこと,ぜひ理解してほしいこと,あるいは習慣的にやっているが根拠がはっきりしないことなどである.必要により根拠となる文献を挙げたので,さらに詳しく知りたい場合の参考になろう. 本書が重症患者危機管理の向上の一助となれば幸いである. 1993年12月 福家伸夫 《目次》 目次 §1.一般管理 1.点滴ラインがとれない 2 2.点滴が漏れている 5 3.動脈ラインの穿刺,留置の技術 7 4.鎖骨下静脈穿刺のコツ 10 5.内頸静脈穿刺の適応とコツ 14 6.大腿静脈穿刺法 17 7.中心静脈カテーテルを切ってしまった 19 8.胃管がうまく入らない 20 9.挿管時に歯を折った,スタイレットが折れた,喉頭鏡のランプがはずれた 22 10.胸チューブ挿入法 24 11.膀胱カテーテル留置 26 12.発熱(あるいは高体温)にはどう対処すればよいか 28 13.閉胸式心マッサージの適応と方法 30 14.開胸式心マッサージ法の適応と踏み切るタイミング 32 15.DCショック(電気的除細動)の原理と方法 34 16.床ずれの対策 36 17.DNRのICUでの適用 38 18.患者の家族が「患者は延命医療を望んでいない」といってきた 40 §2.呼吸管理 1.プレッシャーサポートベンチレーション(圧支持換気)とは何か 44 2.圧支持換気のやり方 46 3.パルスオキシメータの見方 48 4.酸素飽和度と血液内酸素分圧との関係 50 5.カプノグラムの見方 53 6.PETCO2とPaco2の差が大きく,カプノグラムがPaco2の目安にならない 56 7.呼気終末CO2の長期トレンドが病態把握に有効というが 58 8.人工換気中の患者が突然,低酸素血症に陥った 61 9.人工換気中の患者が突然,低酸素血症に陥った.患者に原因があるとすれば,どんなことが考えられるか 63 10.人工換気中の患者が低炭酸ガス血症になった 65 11.人工換気中の患者が高炭酸ガス血症になった 67 12.挿管しようとしたがうまくできない 69 13.患者を人工換気するか否か判断に悩む 73 14.ファイティングへの対応 75 15.気管内チューブの事故抜管にはどのように対処するか 77 16.抜管直後の呼吸困難 79 17.気胸と思われるがレントゲンで見つからない 81 18.胸部外傷で陽圧換気が必要だが,気胸があり,ドレーン挿入に自信がない 83 19.肺塞栓症の診断と治療 85 20.高濃度酸素は有害か 88 §3.循環 1.ショックの分類と治療 92 2.ドパミン/ドブタミンの使用法 94 3.エピネフリン,ノルエピネフリン,フェニレフリンの使用法 96 4.高血圧緊急症への対応 98 5.頻拍性不整脈はどう治療すればよいか 101 6.徐拍性不整脈はどう治療すればよいか 104 7.陳旧性心筋梗塞の患者が(非心臓)手術後に入室するが,再梗塞の危険性は 106 8.虚血性心疾患を合併した術後患者の管理の要点 108 9.急性心筋梗塞の初期治療 111 10.ニトログリセリンは点滴ラインに吸着される 113 §4.SWAN-GANZカテーテル 1.肺動脈カテーテルの適応 116 2.肺動脈カテーテルをうまく肺動脈内にいれるコツ 118 3.肺動脈カテーテルで正しいデータを得るために 120 4.zone IIIとは何か 122 5.心拍出量測定のコツ 124 6.測定時の呼気終末陽圧(PEEP)の扱い 126 7.SWAN-GANZカテーテルでの二次的データ 127 8.各パラメータの略号,正常値,単位 129 9.肺動脈血ガスを測定したら動脈血より酸素分圧が高くでた.何故か 131 10.体表面積はどうやって求めたらよいか 133 §5.精神・神経 1.意識不明の外来急患への対応 136 2.全身麻酔後にICUに入った患者が覚醒しない 138 3.筋弛緩薬の使用法 139 4.瞳孔サイズを見る意味と注意点 141 5.入院患者がせん妄状態である 144 6.せん妄の原因になる薬物 147 7.慢性透析患者が脳内出血で入室した.透析は可能か 149 8.頭蓋内圧の計り方と管理上の注意点 151 9.低酸素血症なのでPEEP加陽圧換気をしたいが,ICP上昇が不安 153 10.脳死とはどういう状態で,どう診断するか 155 §6.血液 1.どのくらいの貧血が輸血の適応か 158 2.白血球数増加への対応 160 3.白血球数減少への対応 162 4.血小板が80万以上に増加している 164 5.血小板が5万以下に減少している 165 6.DICとは何か 167 7.動脈ラインからの検体を凝固系検査に使用できるか 170 8.成分輸血について 172 9.輸血の合併症 175 10.誤った血液を輸血してしまった際の対応 177 11.GVHDとは何か 179 12.血栓溶解療法の適応と禁忌 181 §7.感染 1.血液培養検査で「コアグラーゼ陰性ブドウ球菌」という報告がきた 186 2.カテーテル敗血症 188 3.カテーテル感染症の予防 190 4.中心静脈カテーテル,肺動脈カテーテルはどのくらいで抜去あるいは交換すればよいか 193 5.敗血症が疑われて中心静脈カテーテルを抜去するのに,適切な入れ替え場所がない.今あるカテーテルにガイドワイヤーを通して,入れ替えても心配ないか 194 6.敗血症の診断 196 7.敗血症性ショックの診断 198 8.敗血症性ショックの治療 200 9.MRSA 202 10.院内感染肺炎 204 §8.栄養・代謝 1.血糖値はどのように,またどのくらいに調節すればよいか 208 2.低血糖の原因と症状 210 3.経腸栄養か中心静脈栄養かの選択 212 4.消化管細菌に対するバリア機構の低下の意味 215 5.高カロリー輸液の糖質は何がよいか 216 6.中心静脈栄養はどのように組み立てるか 219 7.経管栄養はどのように進めるか 221 8.AKBRとは何か 223 §9.特殊な疾患,患者 1.小児の患者が入室してきた.輸液量や人工呼吸器の設定は 226 2.小児の患者が入室してきたが,薬用量は 229 3.腎不全時の投薬法 231 4.腎不全時に抗生物質はどう投与すればよいか 233 5.妊婦が別疾患で入室していた 235 6.妊婦が痙攣で入室してきた.妊娠中毒症だろうか 237 7.風邪薬の大量服用で入院した患者が翌日元気になった.退院させるか 239 8.手術後に入室予定患者が宗教上の理由で輸血を拒否している 241 9.意識不明の救急患者の家族が宗教上に理由で輸血を拒否している 243 10.AIDS感染が不安だ 245 §10.システムトラブル 1.突然停電となり,ICU内のすべての人工呼吸器のアラームが鳴り始めた 248 2.突然中央配管から酸素の供給停止,あるいは低圧となった 250 3.ICU患者の院内搬送 252 4.人工換気を受けている患者を搬送する時の注意点 255 5.入院している重症患者を外国に送る 258 6.ICU患者のMR検査 260 7.圧力の単位 262 8.物質の濃度の単位 264 §11.モニタ 1.動脈圧波型がうまくでない 268 2.動脈ラインの血圧とカフ測定による血圧に差がある.どちらを信用するか 269 3.どんなモニタをつければよいか 271 4.心電図モニタはどのようにつければよいか 273 5.心電図モニタにハムが混入する 275 索引 277