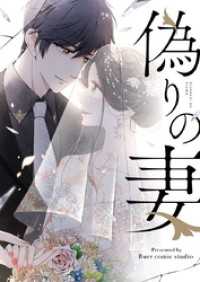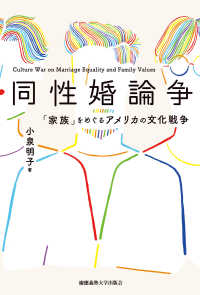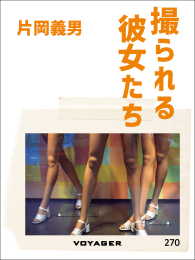出版社内容情報
100年安心は、まやかしなのか、不安を煽ったのは、誰か──。
2025年、国民の5人に1人が後期高齢者になる。この国の年金制度はどうあるべきなのか。その解は、年金官僚たちの壮絶な攻防のドラマの中にちりばめられている。
***
私は「年金ブーム」の1年半ほど、ほぼ毎号、『週刊ポスト』の年金取材に明け暮れた。徹夜もしょっちゅうだったが、20代後半という若さ、知識を吸収する喜びがあり、記者としての手ごたえを感じた時期だ。私の記者人生の〝青春〟であった。
ただし、いくらメディアが激しく批判をしたところで、法律が大きく修正されることはなく、順調に成立した。社会保険庁は解体に追い込まれたが、それで国民生活が良くなったのか、今もって実感がない。
恥を忍んで言えば、「マクロ経済スライド」が人口減少、平均余命の延びによる調整に過ぎないことを、私は本書の取材で初めて理解した。制度の本筋とずれた所を、懸命に掘り下げていたのである。年金取材にどっぷり浸かった私ですらそうだから、一般国民が知るよしもないだろう。
2005年に『週刊文春』に移籍してからも、編集部は私に、年金の記事を数多く担当させてくれた。年金は、私にとって〝背骨〟のような取材対象であり続けた。
本来、私は記者として何を報じるべきだったのか。こうまでメディアを、私を、惹きつける年金とは一体何なのか──。それを解き明かし、ノンフィクション作品として世に問いたいと決意したのが、本書執筆の動機である。
内容説明
国民の年金不信がとまらない。これまで年金改革という錦の御旗のもと、いったい何が繰り広げられてきたのか?国民の不安を募らせる年金ブームを煽ったのは誰か?改革を先送りする年金官僚は、この国の年金制度をどうしたいのか?20年以上にわたり年金問題を取材し続けてきた『週刊文春』記者が、政治とメディア、そして巨額の積立金に翻弄されたエリートたちを描く渾身のノンフィクション!
目次
序章 元霞が関トップの“遺言”
第1章 まやかしの「100年安心」
第2章 小山学校
第3章 年金局長の野望
第4章 河童の涙
第5章 年金不信の正体
第6章 大蔵省資金運用部
第7章 民主党年金改革の蹉趺
第8章 GPIF改革の真相
終章 残された者たち
著者等紹介
和田泰明[ワダヤスアキ]
1975年生まれ。広島県出身。1997年岡山大学法学部卒業後、山陽新聞社入社。上京後、大下英治事務所を経て、『週刊ポスト』記者に。2004年5月、「小泉首相の年金未納は6年8か月」をスクープ。2005年4月から2024年2月まで『週刊文春』特派記者として、主に政治記事を担当した(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
遥かなる想い
kawa
99trough99
koji
Francis


![BRUTUS(ブルータス) 2026年 1月15日号 No.1045 [理想の本棚。]](../images/goods/ar2/web/eimgdata/EK-2324846.jpg)