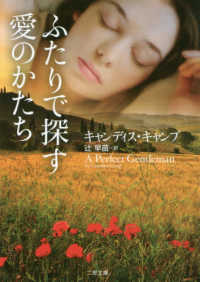出版社内容情報
神道1300年の歴史は日本人の必須教養。「神道」研究の第一人者がその起源から解き明かす。ビジネスエリート必読書。
明治以降の近代化で、「国家総動員」の精神的装置となった「神道」。近年、「右傾化」とも言われる流れの中で、「日本会議」に象徴されるような「国家」の装置として「神道」を取り戻そうとする勢力も生まれている。
では、そもそも神道とは何か。
神道は古来より天皇とともにあった。神道は古代におけるその成り立ちより「宗教性」と「国家」を伴い、中心に「天皇」の存在を考えずには語れない。
しかし「神道」および日本の宗教は、その誕生以降「神仏習合」の長い歴史も持っている。いわば土着的なもの、アニミズム的なものに拡張していった。そのうえで神祇信仰が有力だった中世から、近世になると神道が自立していく傾向が目立ち、明治維新期、ついに神道はそのあり方を大きく変えていく。「国家神道」が古代律令制以来、社会にふたたび登場する。神聖天皇崇敬のシステムを社会に埋め込み、戦争へ向かっていく。
近代日本社会の精神文化形成に「神道」がいかに関わったか、現代に連なるテーマをその源流から仔細に論じる。同時に、「国家」と直接結びついた明治以降の「神道」は「異形の形態」であったことを、宗教学の権威で、神道研究の第一人者が明らかにする。
目次
【第1部 神道の源流】
第1章 神道の起源を考える
第2章 神仏分離の前と後
第3章 伊勢神宮と八幡神
【第2部 神道はどのように生きのびてきたか】
第4章 天津神と国津神
第5章 神仏習合の広まり
第6章 中世から近世への転換
【第3部 近世から近代の神道の興隆】
第7章 江戸時代の神道興隆
第8章 国家神道の時代の神道
第9章 近現代の神道集団
著者略歴
著・文・その他:島薗 進
島薗 進(シマゾノ ススム)
宗教学者、東京大学名誉教授
宗教学者。上智大学グリーフケア研究所客員所員。大正大学客員教授。東京大学名誉教授。NPO法人東京自由大学学長。日本宗教学会元会長。
1948年、東京都生まれ。東京大学文学部宗教学・宗教史学科卒業。同大学大学院人文科学研究科博士課程単位取得退学。主な研究領域は、近代日本宗教史、宗教理論、死生学。
著書に『宗教学の名著30』『新宗教を問う』(以上、ちくま新書)、『国家神道と日本人』(岩波新書)、『神聖天皇のゆくえ』(筑摩書房)、『戦後日本と国家神道』(岩波書店)などがある。
内容説明
神道1300年の歴史は日本人の必須教養。「神道」研究の第一人者がその起源から解き明かす、ビジネスエリート必読書!明治以降の「国家神道」は異形だった。今を生きる日本人の精神文化形成に「神道」がいかに関わったか。
目次
第1部 神道の源流(神道の起源を考える;神仏分離の前と後;伊勢神宮と八幡神)
第2部 神道はどのように生きのびてきたか(天津神と国津神;神仏習合の広まり;中世から近世への転換)
第3部 近世から近代の神道の興隆(江戸時代の神道興隆;国家神道の時代の神道;近現代の神道集団)
著者等紹介
島薗進[シマゾノススム]
宗教学者。上智大学グリーフケア研究所客員所員。大正大学客員教授。東京大学名誉教授。NPO法人東京自由大学学長。日本宗教学会元会長。1948年、東京都生まれ。東京大学文学部宗教学・宗教史学科卒業。同大学大学院人文科学研究科博士課程単位取得退学。主な研究領域は、近代日本宗教史、宗教理論、死生学(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
- 評価
-





akky本棚
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
アルカリオン
みのくま
渡辺(読書/散歩)
白やぎさん
鴨長石