感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
スターライト
7
下巻は、ソビエト政権誕生から戦前までの作品5篇を収録。巻頭の「五人同盟」は、ある発明によって世界征服を企むはずが、皮肉な結果を生むという諷刺作品。「運命の卵」もある発明が引き起こす騒動を描いていて、人間の欲の深さを映画になりそうなシーンをまじえて活写する。「髑髏蛾」は、髑髏模様の羽根をもつ蝶の新種を求めてアマゾンに渡ったものの…という集中ではちょっと変わった趣向の作品。「危険な発明」「不死身人間」も発明を巡るものだが、前者の騒動を巻き起こした人々が素直に反省するところがおかしい。2013/09/01
酔花
5
上巻と比較するとエンタメ色が強い作品が多くて読みやすい。ブルガーコフ「運命の卵」は詳しくないと言いつつも、しっかり新聞記者に説明しているペルシコフ教授が可愛い。無常観に包まれる幕切れが印象的で、科学が政治に利用されることに対するブルガーコフの危機感を感じる。巨大蛇が人を襲う展開にはB級パニックムービー好きとしては心躍らずにはいられないね。ベリャーエフ「髑髏蛾」はアマゾンの奥地へと髑髏蛾を追って彷徨い込んだ生物学者が辿る数奇な顛末を描いた作品。人目につかぬ秘境における遭遇が幻想味を帯びるのは必然か。2014/03/06
roughfractus02
4
政治と科学は世界を一気に変える。が、五人組が世界を独裁しても民衆は恐れず(「五人同盟」1924)、食糧危機で鶏を一気に巨大化し、大量の卵を誤発注して村が滅びても厳冬が危機を相殺する(「運命の卵」同上)。科学技術重視の体制への批判は、昆虫学者がアマゾンで急激に野生化し(「髑髏蛾」1929)、科学者の留守に村人が装置を動かして地球が湿度100%になり(「危険な発明」1938)、作用を反作用に転化する装置が故障して博士の立場が変わる(「不死身人間」1938)様を描く一方、巻き込まれても変わらぬ民衆を描き続ける。2017/12/11
nata
1
それぞれに特色があり、面白い。しかし上巻に比べて(勝手に思う)ソビエトっぽさは薄い。意外な展開ということで「五人同盟」が好き。2015/09/26
u17
0
月の崩壊による人類の廃頽をえがく、A.N.トルストイ「五人同盟」。爬虫類の成長を大幅に促進する生命光線をえがく、ブルガーコフ「運命の卵」。アマゾンに迷い込んだ学者をえがく、我らがA.ベリャーエフ「髑髏蛾」。埃の消失によって生じる悲劇をえがく、エ・ゼリコーヴィチ(誰?)「危険な発明」。絶対的な虚栄の力をえがく、ゲ・グレブネフ「不死身人間」。ならびに編訳者である深見弾の評論「初期のソビエトSF」が収録されている。「運命の卵」と「危険な発明」は、科学に対する無知と、勝手な誤謬に扇動される民衆の(コメント欄に続12013/12/12
-
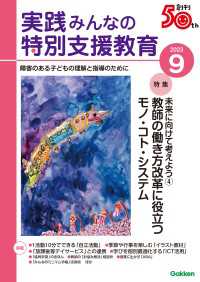
- 電子書籍
- 実践 みんなの特別支援教育 (2023…
-
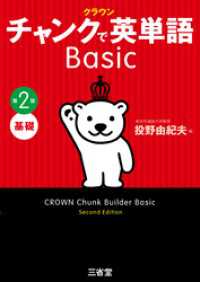
- 電子書籍
- クラウン チャンクで英単語 basic…
-

- 電子書籍
- 愛にむせぶ白鳥〈闇のダリウス、光のザン…
-

- 電子書籍
- 食い詰め傭兵の幻想奇譚8 HJノベルス





